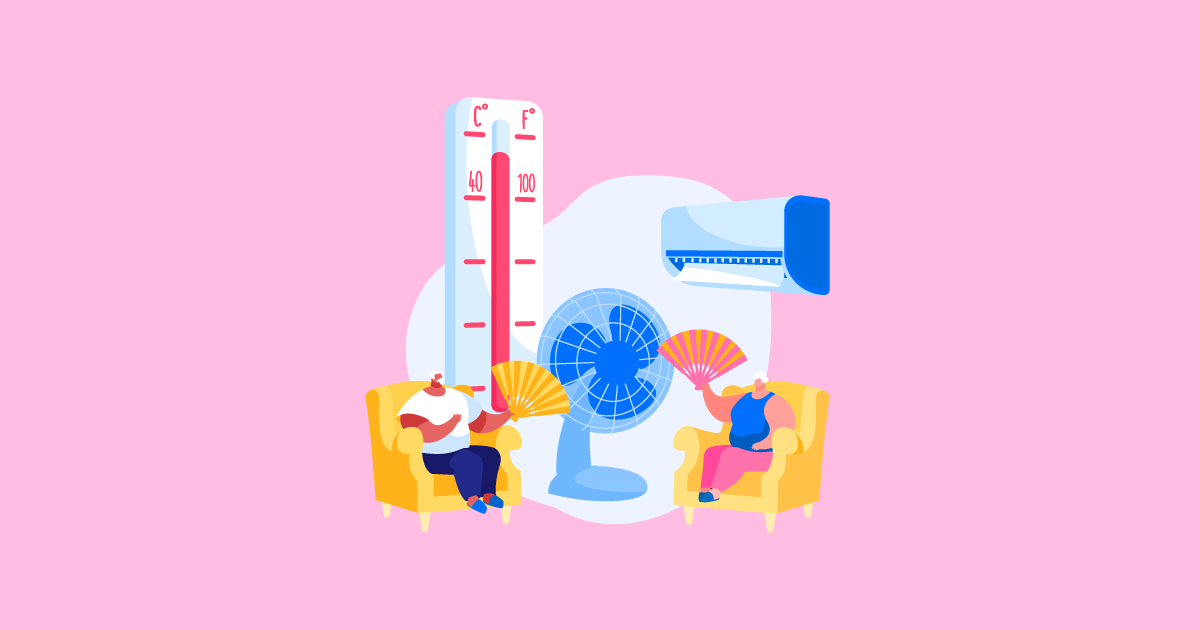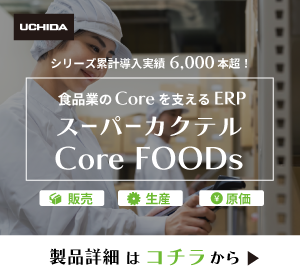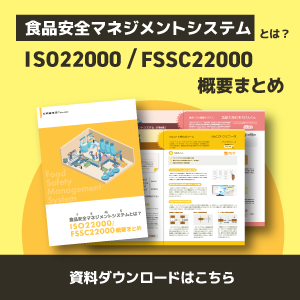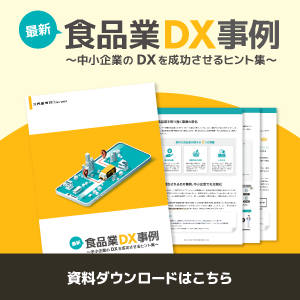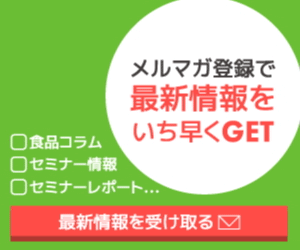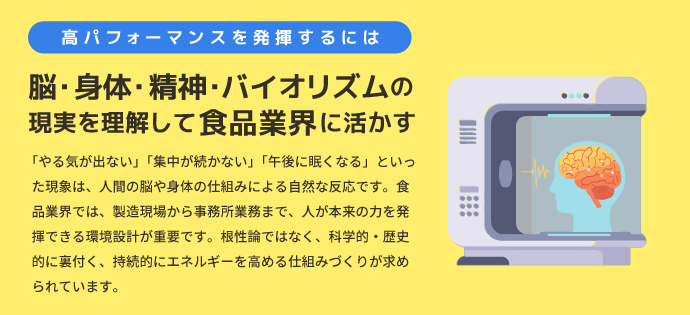
1. はじめに
「やる気が出ない」「集中が続かない」「午後になると眠くなる」。
これらは誰もが経験することであり、特別な現象ではありません。むしろ、人間の脳・身体・精神の仕組みやバイオリズムの現実と限界を考えれば当然のことです。
食品業界の現場である、製造ライン、物流センター、営業活動、さらには本社の事務所業務に至るまで、安全で効率的な仕事をするためには 「人のパフォーマンスを発揮しやすくする」環境設計 が欠かせません。単に「頑張る」「根性で乗り切る」という時代は終わりました。科学的に、そして歴史的に証明されてきた工夫を活かし、持続的にエネルギーを高める仕組みを導入することが求められています。
本稿では、
- パフォーマンスの本質
- エネルギー値や精神のバランス
- 思考・体力のキャパシティ
- 食と眠気の関係
- 脳の時間帯別特性(朝・昼・夕方)
- スポーツ選手の方策や歴史的工夫
- 昨今の企業の取り組み事例
- 食品業界における具体的な展開
を多角的に紹介し、最後に「パフォーマンスは安全に直結する」という観点から、食品業界での実践につなげるヒントを提示します。
1. パフォーマンスとは何か
まず、「パフォーマンス」という言葉は抽象的に使われがちです。ビジネスの場では「成果」や「アウトプット」を意味し、スポーツの場では「記録」や「勝敗への貢献」を意味します。
共通しているのは、
- 一定の条件下で最大限に力を発揮できている状態
- 成果を安定して出し続けられる持久性
一時的に集中して成果を出すことは誰にでもできます。しかし、食品工場のように 毎日、長時間、正確性と安全性が求められる現場では「持続性のあるパフォーマンス」が不可欠です。そのためには、個人のエネルギー値や精神状態を整えることが前提となります。
2. エネルギー値と精神のバランス
人間の身体を「エネルギーを消費するシステム」と捉えると、その仕組みが理解しやすくなります。私たちは常に、脳・身体・精神の三つの側面でエネルギーを消費しています。
- 脳は全エネルギーの約20%を消費
安静時でも脳は体全体の2割のエネルギーを使います。思考や判断、集中作業を行えば、その消費量はさらに増加します。したがって、複雑な業務を長時間続ければ、筋肉よりも先に「脳の疲労」がパフォーマンスを低下させます。 - エネルギー残量を左右する要因
栄養(食事の内容とタイミング)、睡眠(長さと質)、感情の安定度、ストレスの有無などが総エネルギー値を決定づけます。例えば、糖質を取りすぎれば血糖値が乱高下し、精神的にイライラしたり眠気が出たりする。逆に、バランスの良い食事や十分な睡眠は、日中の集中力を高める「エネルギー貯金」となります。 - 精神バランスの乱れが与える影響
精神的に不安定な状態、不安、怒り、焦りが続けば、エネルギー消費は急増します。これは自律神経が常に緊張状態になり、心拍数や血圧、ホルモン分泌が通常より高い水準で推移するためです。その結果、同じ業務をこなすにも「余計な力」を使うことになり、体力のキャパシティを早く使い切るのです。
2-1. 具体例:食品業界での影響
- 製造現場
精神的ストレスが高いと、同じライン作業でも「集中の持続時間」が短くなり、ヒューマンエラーが増える。 - 物流現場
睡眠不足や精神疲労のままフォークリフトを運転すると、判断遅れや事故リスクが急増する。 - 営業活動
精神的に不安定な状態では「相手の反応を読み取る力」が鈍り、提案の質が下がる。 - 事務所業務
小さなトラブルに過敏に反応し、必要以上にエネルギーを使い果たし、午後には集中力が途切れる。
2-2. ポイント
ここで大切なのは「気合い」や「根性」ではありません。
限られたエネルギーをいかに効率よく分配し、精神のバランスを整えて消費を抑えるかが、持続的にパフォーマンスを発揮するための鍵となります。
3. 思考・体力のキャパシティと限界
「キャパオーバー」という言葉が日常で使われるように、人間には処理できる量に明確な限界があります。これを無視すると、どんなに優秀な人でもパフォーマンスが急激に低下し、エラーや事故につながってしまいます。
3-1. 思考のキャパシティ
心理学の古典的研究である 「マジカルナンバー7±2」(ジョージ・ミラー, 1956) によると、人間が同時に保持し処理できる情報量は平均して7前後のチャンク(情報のかたまり)に過ぎません。
- 例えば、製造ラインで「温度」「圧力」「スピード」「品質チェック」「部品供給」など複数の要素を同時に監視していると、すぐに処理能力の限界を超えてしまいます。
- ITシステムやマニュアルで「見える化」「自動化」を進めるのは、人間の思考キャパを補うための仕組みと言えます。
3-2. 体力のキャパシティ
体力の限界は単なる筋肉疲労ではなく、中枢神経系の疲労も深く関与しています。
- 長時間同じ作業を繰り返すと「反応速度」が低下し、判断ミスや動作の遅れが出やすくなります。
- これはスポーツ科学でも「集中力の切れは筋肉ではなく脳の疲労による」と説明されており、工場や物流現場にもそのまま当てはまります。
食品業界では特に立ち仕事や繰り返し動作、重量物の取り扱いが多いため、体力キャパを超えると短期的には「作業スピード低下」や「確認不足」といったエラーにつながります。さらに、無理を続ければ腰痛や腱鞘炎などの慢性的障害を引き起こし、結果的に長期的なパフォーマンス低下につながります。
3-3. 精神のキャパシティ
精神的な負荷もまた「見えない限界」を生みます。
- 不安や怒りなどの強い感情は、前頭前野(意思決定や思考を担う領域)の機能を低下させます。
- その結果、簡単な判断に時間がかかる、確認を忘れる、イライラして周囲と衝突する、といった現象が発生します。
食品工場であれば「チェックリストに印を入れ忘れる」「数値の転記を間違える」といった些細なエラーが、食品安全や品質保証に直結しかねません。
3-4. ヒューマンエラーとキャパシティ超過
食品業界におけるヒューマンエラーは「不注意」だけでなく、キャパシティ超過によって引き起こされるケースが少なくありません。
- ラインスピードが上がった時に、作業者の処理能力が追いつかずチェック漏れが発生。
- 繁忙期の長時間残業で体力と集中力が限界に達し、異物混入や誤出荷が発生。
- 精神的ストレスを抱えた状態でのシフト勤務により、注意力が散漫になり安全確認を失念。
つまり、「人は無限に頑張れるわけではない」という前提に立ち、業務設計そのものをキャパシティに合わせることが必要です。
3-5. まとめ
- 思考は情報の同時処理数に限界がある。
- 体力は筋肉だけでなく神経疲労で制約を受ける。
- 精神は感情やストレスで容量が圧迫される。
これらを理解しないまま「もっと頑張れ」と現場に求めれば、事故や不具合のリスクが高まります。逆に、キャパシティを前提にシステム設計や休憩制度を工夫すれば、パフォーマンスを安定的に引き出せるのです。
4. 食べ過ぎと眠気の関係
「昼食後の眠気」は、多くのビジネスパーソンが経験する現象です。原因はシンプルですが、その影響は職種を問わず大きいものです。
4-1. 昼食後に眠くなるメカニズム
- 食べ過ぎによる血糖値の急上昇
大量の炭水化物や甘いものを摂取すると血糖値が急激に上がり、脳は一時的に活発になります。
- その後の急降下(血糖値スパイク)
上がった血糖値を下げようとインスリンが分泌され、逆に急激に血糖値が下がります。その結果、脳の覚醒度が低下し、強い眠気が訪れるのです。
この生理現象は避けることが難しく、食品工場や物流現場では午後の作業効率低下やミスの増加につながります。また、事務所業務でも同様に、昼食後に集中力が落ちて書類の見落としや入力ミスが増えることは決して珍しくありません。
4-2. 食とパフォーマンスの密接な関係
昼食の摂り方ひとつで、午後のパフォーマンスは大きく変わります。
- 腹八分目を心がけることが午後の集中力を保つ第一歩。
- 炭水化物を控えめにし、タンパク質や食物繊維を組み合わせることで、血糖値の乱高下を防ぎ、眠気を抑えやすくなる。
- 水分補給は代謝を助けると同時に、軽い眠気をリフレッシュさせる効果があります。
さらに、最近では 小分けにした軽食スタイル(例:午前と午後に分けて食べる) や、昼食後に短時間のストレッチや軽い散歩を取り入れる企業も増えています。これは工場・物流現場だけでなく、事務所での知的業務においても有効です。
4-3. 昼食後の仮眠(パワーナップ)の活用
そして、眠気対策として効果的なのが 仮眠(パワーナップ) です。
- 10〜20分程度の短時間仮眠であれば、深い睡眠に入る前に目覚められるため、脳がリフレッシュされ午後の集中力や注意力が改善されます。
- NASAの研究では「26分の仮眠でパフォーマンスが34%向上し、注意力が54%改善した」と報告されており、その効果は科学的にも裏づけられています。
- 工場や物流現場では休憩室での短時間仮眠が事故防止につながり、事務所では机に突っ伏して目を閉じるだけでも効果が期待できます。
4-4. まとめ
つまり、昼食の「量」「内容」「タイミング」を工夫し、さらに短時間の仮眠を取り入れることが、午後の集中・やる気・安全性を大きく左右するのです。
5. 脳の時間帯別特性
人間の脳や身体は、サーカディアンリズム(概日リズム)と呼ばれる約24時間周期の生体リズムに影響を受けています。つまり、1日の中でも「思考が冴える時間帯」と「集中が落ちる時間帯」が存在し、それを無視するとパフォーマンスが下がりやすくなります。
5-1. 朝:思考力のピーク
睡眠によって記憶が整理され、脳の前頭前野がリフレッシュしている時間帯です。
- 特徴
創造的な発想や論理的な判断力が最も高まる。意思決定や新しいアイデアを出す作業に適する。 - 食品業界での活用例
新製品の企画会議や研究開発のブレインストーミングは朝に設定。
営業部門では、新規顧客への提案や戦略立案を午前中に集中させると成果が出やすい。
5-2. 昼:集中力の低下
昼食による血糖値の変動に加え、体内リズムの自然な低下が重なる時間帯です。
- 特徴
覚醒度が下がり、注意力や正確性が落ちやすい。エラー率が高まる。 - 食品業界での活用例
製造現場では、単純作業などリスクが比較的少ない業務を割り当てる。
物流では、在庫確認や伝票整理など、多少集中が落ちても支障が少ない業務に充てる。
事務所では、午前に作成した資料の見直しや承認作業などに適している。
5-3. 夕方:持久的作業に適す
午後から夕方にかけて体温が最も高くなり、筋肉や神経系の機能が安定する時間帯です。
- 特徴
身体機能や持久力が発揮されやすく、ルーティン業務や体力を要する作業に適している。 - 食品業界での活用例
物流部門では、仕分けや積み込みといった作業を夕方に行うと効率的。
工場では、清掃やラインの後処理といった持久的な作業を夕方に回すと無理なく遂行できる。
事務所業務では、メール処理や日報作成などの定型業務に充てると脳のリズムに合いやすい。
5-4. まとめ
このように、脳と身体の時間帯特性を理解し、業務を「最適な時間帯」に割り振ることで、集中力ややる気を無理なく引き出せます。食品業界では特に安全性や品質が重要であるため、時間帯に応じた業務設計は事故防止にも直結します。
6. スポーツ選手の方策
スポーツ界では、トップアスリートが限られた舞台で最高の結果を出すために、パフォーマンスを科学的にコントロールすることが当たり前になっています。これは「気合い」や「根性」に頼るのではなく、栄養・睡眠・精神の調整を組み合わせて、持てる力を最適なタイミングで発揮する工夫です。
6-1. アスリートが実践する主な方法
- 栄養学に基づく食事管理
代表的なのが「炭水化物ローディング」です。試合前に炭水化物を計画的に摂取して体内のグリコーゲン量を増やし、長時間の競技に備えるものです。近年は血糖値の安定を意識した食事法も取り入れられています。 - バイオリズムに合わせた練習・試合時間
人間の体温や覚醒度は一日の中で変化します。たとえば夕方は筋力や持久力が発揮されやすいため、試合やハードな練習をこの時間帯に設定するケースが多くあります。 - メンタルトレーニング
緊張や不安によって集中力が乱れると、身体能力が最大限に発揮されません。呼吸法、イメージトレーニング、マインドフルネスなどを活用し、精神のバランスを整えることが不可欠です。
6-2. 食品業界への応用
食品業界の現場でも、アスリートの工夫は応用できます。
- シフト編成の工夫
体内リズムに合わせて「高集中が必要な工程は午前中」「持久力が問われる作業は夕方」と配置すれば、エラー削減や効率向上につながります。 - 休憩の戦略的導入
アスリートがトレーニング中にインターバルを入れるように、工場や物流でも短い休憩(マイクロブレイク)を取り入れると集中力が持続しやすくなります。 - メンタルケア
作業者が精神的に不安定な状態ではヒューマンエラーが増えます。職場でのリフレッシュ活動や簡単なストレッチ・呼吸法を導入するだけでも、精神バランスの維持に役立ちます。
6-3. まとめ
アスリートは「最高の瞬間」に力を発揮するために科学を活用しています。食品業界でも同じように、人間のリズムやエネルギーを理解し、計画的に整える発想を取り入れることで、安全で効率的な働き方を実現できるのです。
7. 歴史的な工夫
人間は古来より、限られた体力や集中力の中で最大限の成果を出すために、さまざまな工夫を重ねてきました。いずれの時代においても共通していたのは、人間には限界があることを前提とし、その上で持続的に働ける制度や仕組みを設計する姿勢でした。ここでは、古代ヨーロッパから近代の産業革命、そして日本における生活習慣までを概観します。
7-1. 古代ローマ軍団
ローマ軍は遠征時、宿営のたびに通例として標準化された手順で仮設の野営地(カストラ)を築いていました。野営地は四角形に区画を測量し、周囲に堀や土塁・木柵を設けるなど、規則的なレイアウトで整えられていました。こうした周到な準備により、兵士は安心して休養を取り、翌日の戦闘や行軍に備えることができたのです。
つまり、徹底した「場の整備」と「安全の確保」が、そのまま兵士のパフォーマンス維持につながっていたのであり、現代の職場環境づくりにも通じる視点だといえます。
7-2. 中世の修道院
6世紀に制定された聖ベネディクトの戒律は、中世修道院の生活を規律づけました。修道士たちは「時課(canonical hours)」と呼ばれる八つの祈りの時間(夜課・賛課・一時課・三時課・六時課・九時課・晩課・終課)に従い、祈りと学習、労働を一日の中で繰り返しました。この厳格な生活リズムは精神の安定と知的活動の持続を支え、共同生活を長期にわたり維持する仕組みとして機能していました。現代でいえば「メンタルヘルス管理」や「規則正しい勤務制度」の先駆けと位置づけられます。
7-3. 産業革命期
18~19世紀のイギリスでは、工場労働の効率化と引き換えに、過酷な長時間労働や児童労働が深刻な問題となりました。その結果、1833年工場法(Factory Act of 1833)が制定され、9歳未満の就労禁止、児童労働の上限時間、教育の義務化などが法制化されました 。さらに1847年の十時間法(Ten Hours Act)では、女性と若年労働者の労働時間が1日10時間に制限されました 。これらは、事故や健康被害を抑えるために「労働時間を短縮し休息を制度的に保障する」という歴史的な転換点であり、現代の労働安全衛生制度の基盤となっています。
7-4. 日本の工夫 ― 「おやつ」と三食化
日本でも、生活リズムに根ざした食習慣の変化がありました。江戸時代前期までは一日二食が基本でしたが、都市部を中心に江戸中期(元禄期以降)から三食が一般化していきました。また、昼過ぎの「八つ時(午後2時頃)」に軽食を取る習慣が広まり、これが「おやつ」という言葉の由来とされています。
こうした食習慣の変化は、活動時間の長い都市生活に対応する中で生まれた工夫であり、結果的に一度の食事に偏らず、エネルギー補給を分散する形になっていました。現代の「間食で集中力を維持する」考え方と通じる部分があるのは興味深い点です。
7-5. 現代への示唆
こうした歴史的事例はいずれも、人間の身体的・精神的限界を理解した上で制度や習慣を組み立ててきたことを示しています。食品業界においても同様に、シフト設計・作業分担・休憩制度・栄養補給の仕組みを工夫することで、現場の安全性と効率性を両立できるでしょう。
8. 昨今の企業の取り組み例
近年の企業は、従業員のパフォーマンスを高めるために、脳や身体のリズムを前提にした制度を導入しています。その工夫は「睡眠・休憩」だけでなく、「栄養・運動・働き方設計」にまで広がっています。
- 外資系IT企業
Googleはオフィスに仮眠カプセルを設置し、集中力を回復する仕組みを整えています。Nikeは瞑想室を設け、リカバリー時間を確保しています。さらに一部の外資IT企業では、午前中は会議を入れずに集中業務に充てるルールを定め、脳の思考力ピークを最大限に活かしています。 - 製造業大手
ライン作業の集中力低下を防ぐために、マイクロ休憩(数分のリフレッシュ)を取り入れる企業があります。また、昼食後にストレッチや軽運動を習慣化し、血流改善と眠気対策を同時に行う取り組みも進んでいます。 - 食品メーカー
「健康経営」の一環として、従業員の睡眠充足度を指標化するとともに、社員食堂で栄養バランスの良いメニューを提供し、パフォーマンス維持につなげている企業があります。これは「食と集中力」のつながりを意識した好例です。 - 物流企業
長距離輸送を担う企業では、睡眠教育や仮眠制度に加えて、水分補給や食事指導を取り入れています。これにより、ドライバーの疲労軽減と事故防止を両立する成果が報告されています。
8-1. まとめ
これらの事例に共通するのは、「人間の脳・身体・精神のバイオリズムを理解し、それに即した働き方を制度化する」という発想です。食品業界でも、午前の集中業務ルールや昼食後のストレッチ、夜勤での仮眠制度などを組み合わせることで、パフォーマンスと安全性を同時に高められるでしょう。
9. 食品業界における具体的展開
食品業界の現場では、脳や身体のバイオリズムを理解した上で、業務を現実的に調整することが重要です。もちろん、製造ラインや物流は常に稼働しており、単純に「午前だけ集中作業」と区切れるものではありません。しかし、休憩のタイミングや業務の重点配分を工夫することで、パフォーマンスの維持と安全性向上を両立することが可能です。
9-1. 製造現場
食品製造ラインは連続稼働が基本であり、危険工程を午前に集中させることは現実的ではありません。その代わりに、午前中の注意力が高い時間に設備点検や品質チェックの重点確認を行い、午後はこまめなマイクロ休憩を挟みながら単純作業や補助作業を維持するといった工夫が有効です。こうした「時間帯に応じた強弱の付け方」によって、エラーリスクを減らせます。
9-2. 物流部門
物流は納品時間に縛られるため、計画をすべて朝に終えることは難しい場合があります。しかし、出発前の計画や最終確認を午前に重点的に行い、午後は荷下ろしや整理作業の合間に短い休憩や軽運動を組み込むといった工夫が現実的です。特に夕方以降は体力が落ちやすいため、誤配送防止や事故防止の観点からも「チェックリスト方式」や「二重確認」を強化することが効果的です。
9-3. 営業・事務所業務
営業や事務作業では比較的自由度が高いため、午前=思考や判断力を要する業務、午後=整理・処理系の業務という時間帯の特性を活かした業務設計が可能です。
9-4. まとめ
食品業界での応用は、「時間帯ごとの完全な業務振り分け」ではなく、バイオリズムを理解した休憩・重点確認・チェック体制の設計として取り入れるのが現実的です。これにより、安全性と効率を両立する働き方が可能になります。
10. パフォーマンスと安全の関係
食品業界で最も強調すべきなのは、パフォーマンスの維持はそのまま安全の確保につながるという点です。パフォーマンスが低下すれば、単に生産性が落ちるだけではなく、重大なリスクが発生します。
- 集中力の低下
注意力が散漫になることで、機械操作や危険工程での事故リスクが増大します。これは一瞬の判断ミスが大きな労災につながる製造現場において特に深刻です。 - 睡眠不足
長時間労働や夜勤で睡眠が不十分になると、物流現場での交通事故リスクが高まります。国土交通省の調査でも、居眠り運転や疲労による事故は依然として多く報告されており、睡眠とパフォーマンスの関連は明白です。 - 精神バランスの乱れ
強いストレスや感情の不安定さは、単純なミスの増加だけでなく、職場の人間関係の悪化にもつながります。人間関係の不調和は組織全体の安全文化を損ない、さらなる事故リスクを生む温床となります。
したがって、パフォーマンスを整えることは「品質・効率・安全」の三位一体の基盤であり、単なる業務効率化の施策にとどまりません。食品業界においては、従業員の脳・身体・精神のバランスを整えることこそが、最終的に「安心・安全な食品を消費者に届ける」という使命を果たす根本的な手立てとなるのです。
11. おわりに
「パフォーマンスを発揮しやすくする」ことは、決して個人の努力や一時的な工夫にとどまりません。むしろ、組織として制度的に取り組むべき経営課題です。
- エネルギー値を高める工夫
- 精神のバランスを保つ仕組み
- 思考・体力のキャパシティを踏まえた業務設計
- 食事・休憩・シフトの改善
- スポーツや歴史に学ぶ知恵
- 他企業の実践例を参考にした制度化
これらを総合的に組み合わせてこそ、食品業界の現場において、安全かつ効率的なパフォーマンス発揮が可能となります。
「人間の脳・身体・精神の特性を理解し、そのリズムに沿った仕組みを構築すること」は、組織において広く求められる姿勢だと言えるでしょう。
そして、それは大がかりな改革から始める必要はありません。たとえば、
- 午前中の1時間を“集中業務時間”として確保する
- 昼食後に5分間のストレッチや仮眠を導入する
- 週1回だけでも栄養バランスを意識した食事を社内で提供する
こうした小さな取り組みを一つずつ積み重ねるだけでも、組織全体のパフォーマンスと安全性は着実に高まっていくでしょう。

利益改善コンサルタント
資格・スキル活用コンサルタント
技術士合格講師
小松 加奈 氏
日系大手製造業に勤務しながら(2007年新卒入社、技術系総合職)、複業として個人事業も展開している。
工場現場担当者の経験もある、現役会社員の技術士。最前線で『リアルタイム』の『現場』『現物』『現実』『最新技術』と日々向き合っている。
勤務先では、開発部・工場(開発課・製造課・生産管理課)・商品部・生産本部生産管理部にて、工場現場から、本部での管理業務、生産原価管理システム構築、新設工場の生産管理業務構築まで務める。原価改善プロジェクト多数実施。改善・原価教育多数実施。
個人事業では「製造業特化型コンサルティング」「完全カスタマイズ型コンサルティング(全業種対象)」「資格・スキル活用コンサルティング」「技術士合格講座(一般部門全20部門対象)」を展開。
科学技術分野の文部科学大臣表彰(文部科学省主宰)の技術審査員も務め、400件以上の製造業改善事例を審査。
利益改善に関するコンサルティングや、合格に導く技術士受験指導にも定評がある。
【 資格 】
技術士(経営工学部門)、第一種衛生管理者、ハム・ソーセージ・ベーコン製造技能士、フォークリフト運転技能、フードコーディネーター 他
利益改善コンサルタント 技術士 小松加奈website
24時間を楽にする技術【技術士 経営工学部門 小松加奈】
技術士が経営工学技術をもとに、『24時間公私ともに楽にする技術』を『誰でも今すぐ使える』形でわかりやすく伝授❗❗
【2週間ごとに金曜日19時投稿】
【本コラムに関する免責事項】
当サイトへの情報・資料の掲載には注意を払っておりますが、
最新性、有用性等その他一切の事項についていかなる保証をするものではありません。
また、当サイトに掲載している情報には、第三者が提供している情報が含まれていますが、
これらは皆さまの便宜のために提供しているものであり、
当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被ったいかなる損害についても、
当社および当社に情報を提供している第三者は一切の責任を負うものではありません。
また第三者が提供している情報が含まれている性質上、
掲載内容に関するお問い合わせに対応できない場合もございますので予めご了承ください。