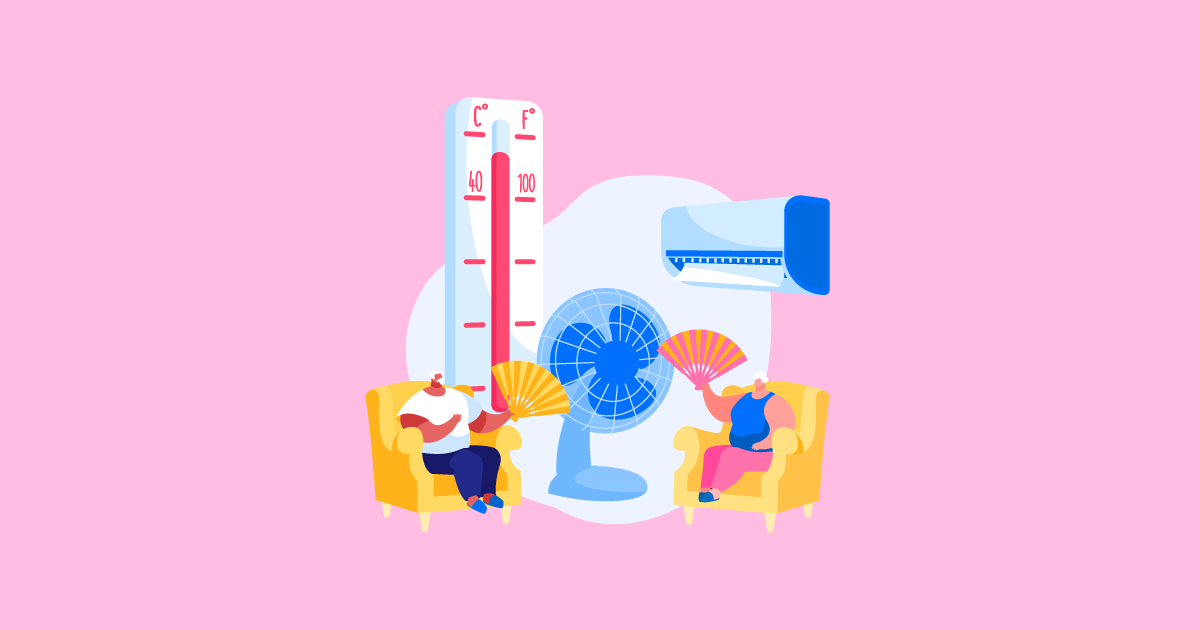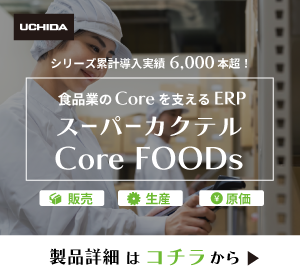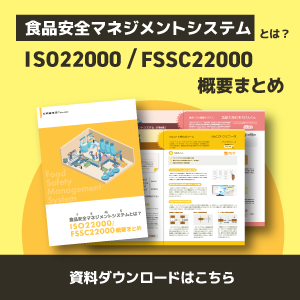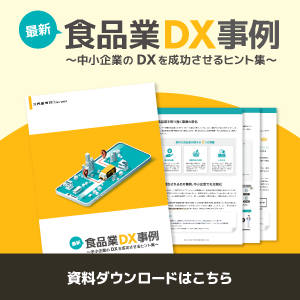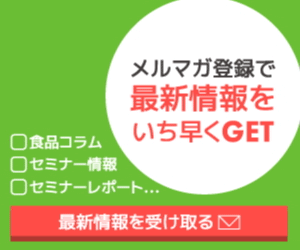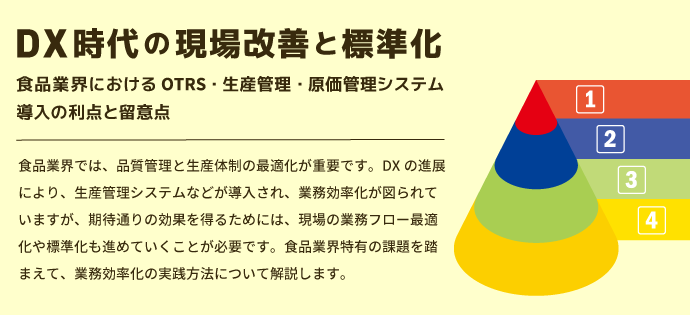
1. はじめに
食品業界は、消費者の健康と安全を守るため、徹底した品質管理と生産体制の最適化が求められる業界です。食品の生産・加工には、生鮮食品・加工食品・冷凍食品など多岐にわたる製品カテゴリがあり、それぞれに異なる品質管理基準や衛生管理規則が適用されます。また、食品ロスの削減や持続可能な生産体制の構築も、近年の重要な課題となっています。
このような中、DX(デジタルトランスフォーメーション)が進み、食品業界でもOTRS・生産管理システム・原価管理システムの導入が加速しています。これらのシステムは、生産工程の可視化・業務効率化・コスト削減・トレーサビリティ強化などの目的で導入され、従来の手作業中心の業務プロセスを効率化する役割を担っています。
しかし、DXを導入した企業の中には、期待通りの効果を得られないケースも少なくありません。これは、デジタル技術の活用だけではなく、現場の業務フローの最適化や標準化が十分に進められていないことが原因として挙げられます。
本コラムでは、食品業界特有の課題を踏まえながら、DXと現場改善の関係性・標準化による業務最適化・人材育成と技術士の視点・動作分析と業務効率化の実践方法について詳しく解説します。
2. DXが進んでも、なぜ現場改善と標準化が必要なのか?
食品業界では、生産管理のデジタル化が進んでいます。具体的には、以下のようなDX施策が多くの企業で導入されています。
- MES(製造実行システム)による生産工程のデータ可視化
- RPA(業務自動化ツール)による作業の省人化
- IoT機器を活用した設備の遠隔監視と予防保全
しかし、DXを導入しても、次のような課題が発生するケースが多く見られます。
2-1. 現場作業のばらつきが大きく、品質が安定しない
食品製造現場では、オペレーターの熟練度によって作業スピードや品質が異なり、製品の仕上がりに差が生じることが多くあります。例えば、パンの成型作業や寿司のシャリの量など、手作業が介在する工程では個人の技量に依存する部分が多いため、ばらつきをなくすためには、作業の標準化が必要になります。
2-2. DXを導入しても、手作業の業務が減らない
食品工場では、工程ごとの衛生管理が厳しく求められるため、自動化の導入が難しい作業も多く残っています。例えば、食品の異物混入チェックやパッケージング工程など、機械化が進んでいても、最終的には人の目視検査や手作業が必要になるケースが多いのが現状です。
2-3. KPI(重要業績評価指標)が設定されておらず、DXの効果が測定できない
食品業界では、歩留まり率・廃棄率・生産リードタイムといった指標が重要ですが、DX導入後もこれらの指標を適切にモニタリングし、さらに現場へフィードバックしないと、「結局、業務効率が上がったのか?」が不透明なままになってしまうことがあります。
このような課題を解決するためには、DXの導入と並行して「現場改善」と「標準化」を進めることが重要です。
3. 食品業界における現場改善の視点
現場改善を成功させるためには、「現場・経営層・取引先・顧客」の視点を持つことが重要です。
3-1. 現場の視点:作業の標準化と最適化
- HACCP(危害分析重要管理点)やトレーサビリティの確保が重要
- 作業のムダを削減し、最適な動作を標準化することで、ばらつきをなくす
3-2. 経営層の視点:KPIを活用した評価
- 生産性向上のために、「歩留まり率」「生産コスト」「リードタイム」といったKPIを設定
- リアルタイムでデータ分析を行い、改善の進捗を可視化する
3-3. 取引先・顧客の視点:安定供給と品質向上
- 安定した供給能力を確保するため、適正在庫の維持と無駄な仕入れの削減が重要
- 品質の安定化が顧客満足度向上につながる
4. 人材育成と技術士の視点
4-1. DX時代の食品業界に求められる人材育成
食品業界におけるDXの進展により、自動化やデジタル技術の導入が進む一方で、それを活用するための「人材のスキル向上と組織的な教育体制の確立」が不可欠となっています。特に、食品業界では生産現場の現場力が経営の競争力に直結するため、単なる技術導入ではなく、従業員が新しい環境に適応し、生産性を向上させる仕組みを整えることが求められます。
例えば、現場従業員のデータ活用能力の向上が重要です。従来、食品工場では経験と勘に頼った作業が多かったため、DX導入後もデータを有効活用できない企業が少なくありません。そこで、データをもとに問題を分析し、改善策を立案できるスキルを持つ管理者の育成が急務となります。
また、従業員の教育・研修制度を強化することで、食品安全の管理手法(HACCPなど)の理解を深めるだけでなく、IoTやAI技術を活用したスマートファクトリー化に対応できる人材の育成が可能になります。
4-2. 技術士の視点を活かした食品業界の改善手法
技術士は、科学技術を活用して業務の最適化を図る専門家であり、食品業界においても生産工程の改善や品質管理の強化に大きく貢献できます。例えば、経営工学部門の技術士が食品工場で活躍する場合、以下のような視点で改善活動を進めることが可能です。
- 作業動作の最適化によるムダの削減(IE:インダストリアル・エンジニアリング手法)
- 生産ラインのボトルネック分析と工程改善
- 原材料・エネルギー使用量の最適化によるコスト削減
- DXの導入による業務プロセスの自動化とデータ管理の効率化
食品業界において技術士の考え方を取り入れることで、単なるシステム導入ではなく、継続的な業務改善と組織全体の生産性向上を実現することが可能となります。
5. 動作の具体化と効率化のポイント
~OTRSの活用による改善事例~
5-1. なぜ「動作の具体化」が必要なのか?
食品業界の製造現場では、作業者の動きによる生産性のばらつきが大きな課題となっています。例えば、同じラインで作業しているにも関わらず、作業者ごとに作業スピードが異なるケースが見られます。これは、作業の標準化が十分に行われておらず、無駄な動作や不要な手順が発生しているためです。
動作の具体化とは、作業工程を細かく分解し、最適な動作を明確にすることで、生産性向上と業務の標準化を実現する手法です。このプロセスを実施することで、以下のようなメリットが得られます。
- 作業のバラつきをなくし、生産効率を向上させる
- 無駄な動作を削減し、作業者の負担を軽減する
- 標準作業を確立することで、新人教育を効率化する
- 業務の属人化を防ぎ、品質の安定性を高める
5-2. OTRSとは?
食品業界では、こうした作業の最適化を行うために「OTRS(Operations Time Research Software)」が活用されています。OTRSは、作業をビデオで録画し、動作を細かく分析することで、最も効率的な作業パターンを導き出し、標準化を進めるためのソフトウェアです。
OTRSの主な機能
- 作業分析:
・作業者の動きを映像で記録し、どの動作に時間がかかっているかを分析
・無駄な動作や不要な動きが可視化される - 標準作業の作成:
・最適な動作パターンをデータとして蓄積し、誰でも同じ手順で作業できるようにする
・標準作業書の作成や、教育用マニュアルの整備が容易になる - 業務の最適化:
作業のばらつきを抑え、食品加工・包装・梱包などのプロセスを統一
作業スピードを平均20~30%向上させるケースもある
5-3. OTRSを活用した食品業界の改善事例
事例①:食品加工ラインの作業標準化
ある食品メーカーでは、冷凍食品の盛り付け作業において、作業者ごとの処理時間に大きな差があり、1日あたりの生産量が安定しないという問題が発生していました。特に、ベテラン作業者と新人の間では、作業スピードに最大30%の差があり、生産計画の見直しが頻発する状況でした。
- OTRSを活用し、作業者の動作を録画・分析
- 作業の流れを時間ごとに分解し、無駄な動作を洗い出し
- 最も効率的な動作パターンを設定し、標準作業マニュアルを作成
- 新人研修にOTRSのデータを活用し、作業習熟期間を短縮
- 作業スピードのバラつきが減少し、生産効率が15%向上
- 作業者の負担が軽減され、ミスの発生率が20%削減
- 新人の研修期間が30%短縮され、戦力化が早まった
事例②:食品工場の包装工程の最適化
大手食品メーカーの包装工程では、商品ラベルの貼付作業で、作業者によってミスが発生しやすいという問題がありました。また、作業手順が標準化されておらず、作業者によって手順が異なり、ミスの発生率が高くなっていました。
- OTRSを導入し、ラベル貼付作業を詳細に分析
- 作業工程の最適な動作を標準化し、すべての作業者が同じ手順で作業できるように指導
- 手の動かし方や作業の順番を最適化し、無駄な動作を削減
- ミス発生率が40%低下し、品質の安定化に成功
- 作業スピードが10%向上し、1時間あたりの生産量が増加
- 新人研修の時間を50%短縮し、作業習熟の効率化に貢献
5-4. OTRS導入のメリットと食品業界特有の注意点
OTRSは、食品業界における動作の具体化と最適化に非常に有効ですが、導入にあたっては以下のポイントを押さえておく必要があります。
【メリット】
- 作業のムダを徹底的に排除し、業務効率を最大化できる
- 標準作業を作成し、誰が作業しても同じ品質を維持できる
- 作業映像を活用した教育が可能になり、新人育成を効率化できる
【注意点】
- 食品製造現場では衛生管理が最優先であるため、作業の見直しがHACCPやISO22000、FSSC22000などの規格と整合しているか確認が必要
- 手作業が多い食品工場では、作業者の習熟度や技能の向上を並行して進めることが不可欠
- OTRS導入後も定期的な分析を行い、改善を継続的に行う仕組みが必要
6. 生産管理システムと原価管理システムの導入
ここまで、DXと現場改善の関係性、標準化による業務最適化、人材育成と技術士の視点、動作分析と業務効率化(OTRS活用)について詳しく解説しました。これらの取り組みを進めることで、食品業界における業務の効率化と品質向上が可能になりますが、改善活動を最大限に活かすためには、生産管理システムと原価管理システムの導入も重要です。
生産管理システムと原価管理システムは、単なるデータ管理ツールではなく、業務の効率化・原価の最適化・品質管理の向上を実現するための戦略的なシステムとして活用することが求められます。
6-1. 生産管理システムの利点と導入時のポイント
食品業界では、品質維持・安定供給・生産コスト削減のために、生産管理システムの導入が進んでいます。
【生産管理システムの主な利点】
- リアルタイムで生産状況を把握し、計画変更に迅速に対応
- 設備の稼働率を最適化し、ダウンタイムを削減
- トレーサビリティの強化により、食品安全基準の遵守を確実に
- 歩留まり率の改善により、食品ロスを削減
例えば、冷凍食品の製造現場に生産管理システムを導入したケースでは、原材料の入荷・加工・包装・出荷までの全工程をリアルタイムで可視化することで、リードタイムの短縮・生産効率の向上・在庫最適化が実現しました。
しかし、食品業界の生産管理システム導入では、以下のポイントに注意が必要です。
【導入時の注意点】
- HACCPやISO22000などの食品安全規格への対応
食品業界では、HACCPやISO22000などの厳格な品質管理基準が求められるため、これらの基準を満たす形でシステムを設計することが必要。 - 生産計画の柔軟性の確保
食品は原材料の入荷状況や市場の需要変動による影響を受けやすいため、固定的な生産スケジュールではなく、柔軟に計画変更できるシステム設計が求められる。
6-2. 原価管理システムの利点と導入時のポイント
食品業界では、原材料費やエネルギーコストが経営に大きく影響するため、原価管理システムの導入が効果的です。
【原価管理システムの主な利点】
- 原材料の仕入れ状況をリアルタイムで把握し、適正在庫を維持
- 食品ロス削減によるコスト最適化
- 利益率の可視化により、価格設定戦略を最適化
例えば、原価管理システムを活用して原材料の使用効率をリアルタイムで監視することで、不要な廃棄を削減し、コスト削減につなげた事例があります。
【導入時の注意点】
- リアルタイムなデータ活用による原価計算の精度向上
原材料の価格変動や、賞味期限が近い材料の優先使用を考慮した在庫管理機能が必要。 - トレーサビリティの確保によるコスト管理
どの工程でコストが発生しているかを詳細に分析し、無駄なプロセスを削減するためのデータ可視化が必要。
7. まとめ
食品業界におけるDXの成功には、「現場改善」「標準化」「評価の見える化」「人材育成」「専門家(例:技術士)の視点」「動作分析と業務効率化(OTRS活用)」「生産管理・原価管理システム導入」が重要です。
これらをバランスよく進めることで、食品メーカーは、持続可能な生産体制の構築と競争力の向上を実現することが可能になります。
- デジタル化と並行して、現場改善の基本を押さえる
- KPIを設定し、継続的な改善活動を進める
- データを活用した標準化と最適化を実践する
- 技術士の視点を活かし、DXと現場改善を融合する
特に、食品業界では、HACCPやISO22000といった品質基準への適合や、食品ロス削減・安全性確保を両立するためのシステム導入が求められるため、単なるIT導入ではなく、業務改善と並行したシステム活用が重要になります。
本コラムが、食品業界におけるDXと業務改善の取り組みを進める上でのヒントになれば幸いです。

利益改善コンサルタント
資格・スキル活用コンサルタント
技術士合格講師
小松 加奈 氏
日系大手製造業に勤務しながら(2007年新卒入社、技術系総合職)、複業として個人事業も展開している。
工場現場担当者の経験もある、現役会社員の技術士。最前線で『リアルタイム』の『現場』『現物』『現実』『最新技術』と日々向き合っている。
勤務先では、開発部・工場(開発課・製造課・生産管理課)・商品部・生産本部生産管理部にて、工場現場から、本部での管理業務、生産原価管理システム構築、新設工場の生産管理業務構築まで務める。原価改善プロジェクト多数実施。改善・原価教育多数実施。
個人事業では「製造業特化型コンサルティング」「完全カスタマイズ型コンサルティング(全業種対象)」「資格・スキル活用コンサルティング」「技術士合格講座(一般部門全20部門対象)」を展開。
科学技術分野の文部科学大臣表彰(文部科学省主宰)の技術審査員も務め、400件以上の製造業改善事例を審査。
利益改善に関するコンサルティングや、合格に導く技術士受験指導にも定評がある。
【 資格 】
技術士(経営工学部門)、第一種衛生管理者、ハム・ソーセージ・ベーコン製造技能士、フォークリフト運転技能、フードコーディネーター 他
利益改善コンサルタント 技術士 小松加奈website
24時間を楽にする技術【技術士 経営工学部門 小松加奈】
技術士が経営工学技術をもとに、『24時間公私ともに楽にする技術』を『誰でも今すぐ使える』形でわかりやすく伝授❗❗
【2週間ごとに金曜日19時投稿】
【本コラムに関する免責事項】
当サイトへの情報・資料の掲載には注意を払っておりますが、
最新性、有用性等その他一切の事項についていかなる保証をするものではありません。
また、当サイトに掲載している情報には、第三者が提供している情報が含まれていますが、
これらは皆さまの便宜のために提供しているものであり、
当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被ったいかなる損害についても、
当社および当社に情報を提供している第三者は一切の責任を負うものではありません。
また第三者が提供している情報が含まれている性質上、
掲載内容に関するお問い合わせに対応できない場合もございますので予めご了承ください。