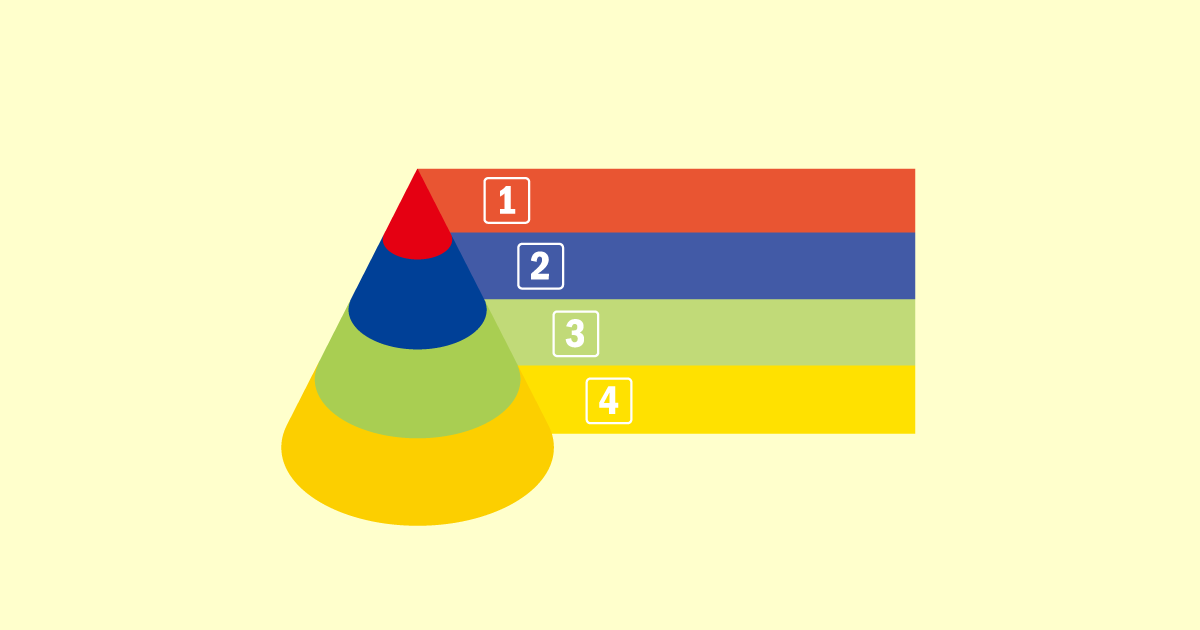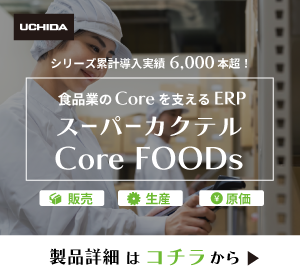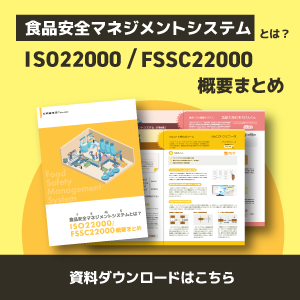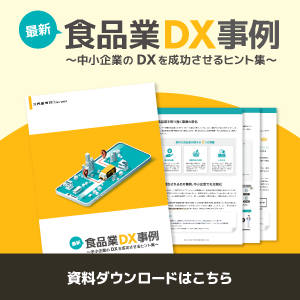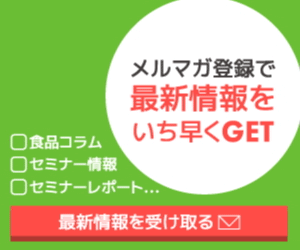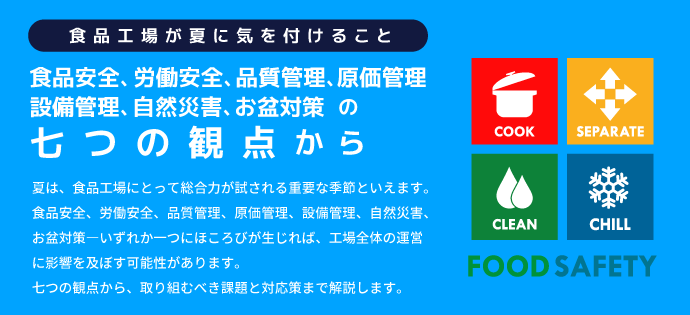
1. 食品安全
― 微生物とウイルス、夏の見えにくいリスクを見つめる
1-1. 背景と重要性
夏場の食品工場では、高温多湿の環境が細菌の増殖を急速に後押しします。黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ、サルモネラなどの細菌は、わずかな温度逸脱や滞留時間の延長で爆発的に増殖し、重大な食品事故につながりかねません。
一方で、見落とされやすいのがウイルスリスクです。ノロウイルスは冬場の流行が有名ですが、夏も食品従事者の不顕性感染(症状がないままの保有)によって工場内に持ち込まれる可能性があります。また、A型肝炎ウイルスは、海外由来の冷凍果物や魚介類の輸入品でリスクが指摘されており、夏場の生食需要増加に伴う注意が必要です。
現場のリアル
- クール便のトラック荷下ろし後、荷捌き場で30分放置され、表面温度が急上昇
- 作業者が熱中症対策で水分補給するが、その後の手洗いが不十分
- 調理後の冷却が追いつかず、中心温度が高いまま冷蔵庫へ格納される
1-2. 問題と落とし穴
- 汗・皮脂汚染:夏の汗は1時間で1L近く。帽子・マスク・手袋の装着状態が甘くなりがち
- 冷却のボトルネック:急速冷却機の能力不足、氷水の不足、作業標準の不徹底
- 洗浄殺菌の見落とし:排水口・パッキン・コンベア裏など、夏場はヌメリ急増
- 検品体制の緩み:暑さで作業者の集中力が落ち、異物・異常品の見落としが増加
1-3. 実践的対応策
- 温湿度のリアルタイム管理
IoTロガーを各エリアに設置し、逸脱時に即アラート - 冷却工程の強化
急速冷却機の増設、氷水バット使用、冷却開始・終了のタイムチャート化 - 個人衛生の再教育
冷感素材の作業着、手袋・帽子・マスクの交換回数増。特に「汗による異物混入」や「トイレ後の手洗い」の重要性を現場で再確認 - ウイルス対策の重点強化
下痢・嘔吐症状の自己申告ルールの徹底。石けんと流水による手洗い重視(アルコールはノロウイルスには効果が限定的)。調理器具・まな板・ふきんの次亜塩素酸殺菌 - 仕入れ品の確認
海外産の冷凍果実・魚介類などのウイルス対策状況をサプライヤーと確認。必要に応じて加熱や殺菌工程を見直す
1-4. 課題と展望
食品安全は「全員の意識と行動の積み重ね」で成り立っています。細菌対策は数値管理や工程設計で比較的管理しやすい一方、ウイルスは人由来の媒介が主なため、作業者の衛生意識や体調管理が鍵を握ります。
今後は、
- ウェアラブル端末による体調・衛生状況の把握
- AIやセンサーを使った異常検知・予兆保全
- 派遣・臨時スタッフ向けの短時間・実技重視の衛生教育
など、技術と教育の両輪で安全管理を進めることが一層重要になってきます。
2. 労働安全 ― 熱中症、事故、人的リスクの見逃しは命取り
2-1. 背景と重要性
工場では食品の温度管理ばかり注目されがちですが、作業者の体温管理こそ最大の労働安全課題です。夏の工場内、加熱調理エリアでは体感40℃、冷蔵庫内と外の温度差は30℃。一歩間違えば熱中症、意識障害、転倒事故が起こります。
現場のリアル
- 加熱室で汗だくの作業員が意識を失い、コンベアに倒れ込む
- 搬入出作業中、頭がボーッとしてフォークリフト接触事故
- 休憩室が暑く、作業中より疲弊する
2-2. 問題と落とし穴
- WBGT(暑さ指数)の未管理:気温・湿度・輻射熱を無視して「空調は入っているからOK」と過信
- 休憩・給水の形骸化:休憩室が遠い・混雑・気まずさで行かない
- 作業服の選定ミス:通気性の悪い防塵服、冷房が効かないエリアでの密閉着用
- 高齢者・基礎疾患持ちのリスク無視:一律の作業割り当て
2-3. 実践的対応策
- エリア別WBGT値掲示、リアルタイムモニタ
- 30分に1回の強制休憩、冷水・塩飴・経口補水液の支給
- 冷却ベスト・ファン付き作業服の採用
- 健康チェックシート、心拍・体温ウェアラブル管理
- 配置換え(例:高齢者は加熱室から包装室へ)
2-4. 課題と展望
「安全と効率のせめぎあい」が最大課題。作業者側からも「自己管理」を促す教育、そして体調・ストレスを見える化する人事管理のデジタル化が今後の鍵です。
3. 品質管理 ― 温度・時間・人の管理で守る製品価値
3-1. 背景と重要性
品質管理は単に「不良品を減らす」ではなく、「価値を守り抜く」活動です。夏場は温度変化、湿度上昇で劣化速度が急上昇。例えば、チルドデザートではpH変動、冷凍品では解凍→再冷凍で氷結晶の変化による食感悪化が起こります。
現場のリアル
- チルド便積み替え時の庫外で、短時間の温度逸脱
- ライン停止時、仕掛品が放置され表面乾燥や結露
- 包材が高温で変形し、ヒートシール不良発生
3-2. 問題と落とし穴
- 滞留時間の見逃し:加熱後、冷却後、包装前での滞留が長い
- 包材の選定・保管:夏場の高温で包材が粘つき、成形不良
- 酸化・変色リスク:油脂製品の酸化、青果の変色、肉の退色
3-3. 実践的対応策
- 工程間の滞留時間短縮(例:冷却→包装直結ライン導入)
- 包材の温度管理、熱安定性の事前試験
- 夏季専用の酸化防止剤・窒素充填比率見直し
- 出荷前のランダム抜取検査頻度増
4-3. 課題と展望
「わかっていても間に合わない」現場対応を超え、事前予測(AI・シミュレーション)、包材・レシピの夏仕様開発、温湿度統合モニタリングが今後のテーマです。
4. 原価管理 ― 夏特有のコスト上昇とどう戦うか
4-1. 背景と重要性
夏は電気代のピークシーズンです。冷凍・冷蔵機器の稼働率は冬の2~3倍。加えて、熱中症対策費(冷却ベスト、スポーツドリンク、休憩スペース増設)、廃棄・ロス(品質逸脱品)、自然災害対応(緊急輸送費)。油断すれば、利益率が大幅に低下します。
現場のリアル
- 冷蔵庫の庫内温度逸脱で原料ロット全廃棄
- 猛暑によるライン停止→仕掛品全滅
- 臨時人員増加による労務コスト増
- 予期せぬ原料輸送の空輸手配
4-2. 問題と落とし穴
- エネルギーコスト無視:冷却、冷凍、除湿の電力消費増
- 廃棄・ロスの見過ごし:不良率、作業ミス、異物混入による廃棄増加
- 追加対策費の未予算化:安全対策や設備補強を都度対応
- 調達コストの変動:冷蔵・冷凍原料の夏季割増、緊急輸送費
4-3. 実践的対応策
- ピーク電力回避の生産スケジュール調整
- 廃棄・ロスの見える化(ライン別・時間帯別)と改善PDCA(夏季設定)
- 夏季対策費を予算計画に組み込み、原価計算に反映
- 原料調達の複数ルート確保と価格交渉
- 設備効率向上(例:高効率冷却装置、冷気漏れ防止)
4-4. 課題と展望
コスト管理は「節約」だけでなく「投資判断」。必要な投資は惜しまず、長期視点でのエネルギー効率化、省人化、サプライチェーン強化が求められます。
5. 設備管理 ― 夏は機械も人も悲鳴をあげる
5-1. 背景と重要性
冷凍庫、冷蔵庫、冷却水設備、換気設備、コンプレッサー。夏はすべての設備に過負荷がかかります。気温の高さは、結露・熱膨張・基板ショート・軸受の摩耗といった設備トラブルの直接原因です。
現場のリアル
- コンプレッサーのモーター過熱で緊急停止
- 冷却水配管に結露→漏水→床滑り事故
- 断熱材劣化で冷気漏れ、冷却効率ダウン
- 冷凍庫の霜付着による扉の開閉不良
5-2. 問題と落とし穴
- メンテナンス不足:夏直前の点検未実施、可動時間延長で疲弊
- 小規模設備の見落とし:冷蔵ショーケース、電子秤、制御盤
- 緊急時の応急対応未整備:代替冷却手段、簡易修理体制
5-3. 実践的対応策
- 夏前の全設備保守点検と劣化部品交換
- 結露対策(断熱材補強、防湿シート、排水経路整備)
- フィルター、ファン、冷媒のメンテ頻度増
- 制御盤・基板の防塵・防湿カバー設置
- 設備異常時の代替冷却手段、外部メンテ契約整備
5-4. 課題と展望
今後はIoTによる稼働監視、異常予知、スマートメンテナンスが必須。小規模工場こそ補助金活用で最新技術の導入を検討すべきです。
6. 自然災害 ― 台風・豪雨の物流リスクとBCP
6-1. 背景と重要性
7~9月は台風・豪雨シーズン。道路寸断、港湾閉鎖、鉄道運休で、原料調達・製品出荷は一瞬で麻痺します。食品工場にとって自然災害対策は「起きたら考える」では遅く、事前のBCP(事業継続計画)が命綱です。
現場のリアル
- 台風直撃で港が閉鎖、輸入原料が数日遅延
- 大雨で道路が冠水し、デリバリートラックが到着不可
- 停電で冷凍庫の庫内温度が上昇
6-2. 問題と落とし穴
- 在庫の脆弱性:原料・資材を最低限しか持たない「ジャストインタイム」
- 代替輸送の未確保:通常ルートしか想定せず
- 工場・倉庫の浸水リスク未対策:低地立地、排水設備不備
6-3. 実践的対応策
- 台風前の原料・資材の前倒し搬入
- 代替サプライヤー、輸送ルートの確保
- 緊急輸送費用の予算化と契約書整備
- 工場・倉庫の止水板設置、浸水対策
- 停電時の冷却維持手段(例:ドライアイス、非常用発電機)
6-4. 課題と展望
BCPは「想定外を想定内にする」活動。全拠点の脆弱性マップ作成、複数拠点間の相互バックアップ、自然災害シミュレーション訓練が求められます。
7. お盆対策 ― 繁忙期を制す人・モノ・スケジュール管理
7-1. 背景と重要性
お盆は、需要増と人手不足が同時に襲う特別な時期。納品先も問屋も配送業者も「お盆進行」、工場も「夏休み取得」、全体の歯車が狂いやすい時期です。
現場のリアル
- お盆明け納品が集中し、出荷ラインがパンク
- 臨時人員に依存し、作業ミス多発
- 仕入先の休業に気が付かず原料不足
7-2. 問題と落とし穴
- 需要予測の甘さ:前年実績だけでは足りない
- 休暇計画の未調整:部門間の調整不足
- 購買・調達の詰め不足:お盆前最終納入の確認漏れ
7-3. 実践的対応策
- お盆特別スケジュール(受注・生産・出荷・購買・労務)の全社共有
- 増産体制の臨時人員確保(派遣・アルバイト)と事前教育
- 主要仕入先との納入・休業スケジュール調整
- 配送業者と事前に休日対応契約
- 人事・労務の早期休暇計画提出と要員配置計画
7-4. 課題と展望
お盆時期の現場対応については、どうしても「ギリギリまで現場に負担が集中しがち」という課題が見受けられます。全社的な需給・労務計画のすり合わせや、AI予測を活用した需要の見通し、繁忙期のリスク分散といった取り組みが、今後さらに重要性を増していくと考えられます。
終章:夏を乗り越えるために必要なこと
夏は、食品工場にとって総合力が試される重要な季節といえます。食品安全、労働安全、品質管理、原価管理、設備管理、自然災害、お盆対策――いずれか一つにほころびが生じれば、工場全体の運営に影響を及ぼす可能性があります。こうした課題に対し、現場ではこれまでも日々の努力を積み重ね、部門を越えた連携や、事前の準備・予測を通じて夏のリスクを抑えるために取り組んできました。その地道な積み重ねこそが、夏を確実に乗り越える力となり、工場全体の安定や信頼につながっているのだと感じます。
現場、管理職、経営層がそれぞれの立場で役割を果たし、課題に向き合い続ける姿勢は、今後も食品製造業を支える大切な力といえるでしょう。

利益改善コンサルタント
資格・スキル活用コンサルタント
技術士合格講師
小松 加奈 氏
日系大手製造業に勤務しながら(2007年新卒入社、技術系総合職)、複業として個人事業も展開している。
工場現場担当者の経験もある、現役会社員の技術士。最前線で『リアルタイム』の『現場』『現物』『現実』『最新技術』と日々向き合っている。
勤務先では、開発部・工場(開発課・製造課・生産管理課)・商品部・生産本部生産管理部にて、工場現場から、本部での管理業務、生産原価管理システム構築、新設工場の生産管理業務構築まで務める。原価改善プロジェクト多数実施。改善・原価教育多数実施。
個人事業では「製造業特化型コンサルティング」「完全カスタマイズ型コンサルティング(全業種対象)」「資格・スキル活用コンサルティング」「技術士合格講座(一般部門全20部門対象)」を展開。
科学技術分野の文部科学大臣表彰(文部科学省主宰)の技術審査員も務め、400件以上の製造業改善事例を審査。
利益改善に関するコンサルティングや、合格に導く技術士受験指導にも定評がある。
【 資格 】
技術士(経営工学部門)、第一種衛生管理者、ハム・ソーセージ・ベーコン製造技能士、フォークリフト運転技能、フードコーディネーター 他
利益改善コンサルタント 技術士 小松加奈website
24時間を楽にする技術【技術士 経営工学部門 小松加奈】
技術士が経営工学技術をもとに、『24時間公私ともに楽にする技術』を『誰でも今すぐ使える』形でわかりやすく伝授❗❗
【2週間ごとに金曜日19時投稿】
【本コラムに関する免責事項】
当サイトへの情報・資料の掲載には注意を払っておりますが、
最新性、有用性等その他一切の事項についていかなる保証をするものではありません。
また、当サイトに掲載している情報には、第三者が提供している情報が含まれていますが、
これらは皆さまの便宜のために提供しているものであり、
当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被ったいかなる損害についても、
当社および当社に情報を提供している第三者は一切の責任を負うものではありません。
また第三者が提供している情報が含まれている性質上、
掲載内容に関するお問い合わせに対応できない場合もございますので予めご了承ください。