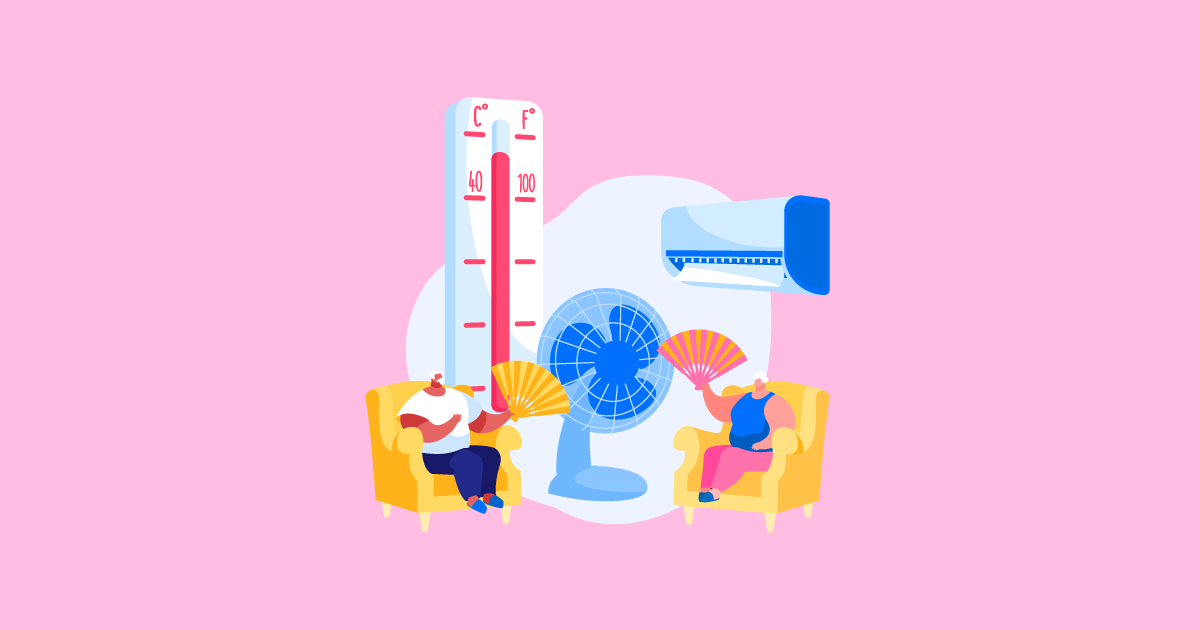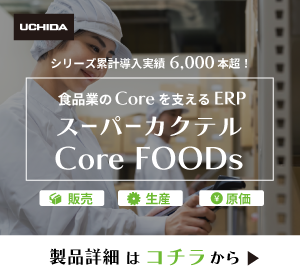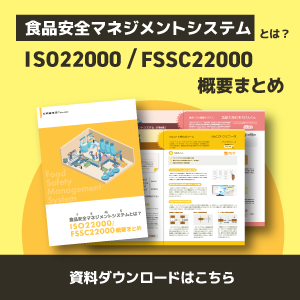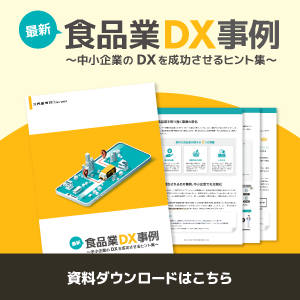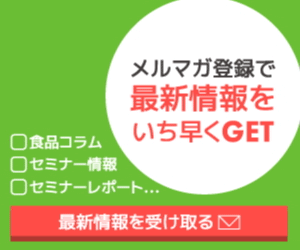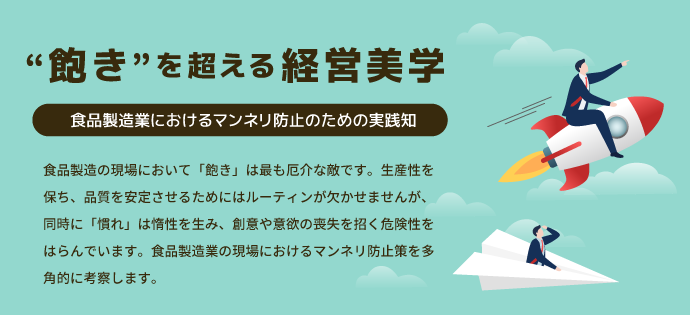
はじめに
食品製造の現場において、「飽き」は地味でありながら最も厄介な敵です。生産性を保ち、品質を安定させるためにはルーティンが欠かせませんが、同時に“慣れ”は惰性を生み、創意や意欲の喪失を招く危険性をはらんでいます。
本稿では、名店「銀座 小十」に学ぶ変化の美学を起点に、さまざまな業界に学びながら、食品製造業の現場におけるマンネリ防止策を多角的に考察します。
第1章:「銀座 小十」に学ぶ──変化と更新を文化にする美学
伝統と革新の融合、それはまさに「銀座 小十」が体現する哲学です。東京・銀座の名店「銀座 小十」では、料理の献立のみならず、器や盛り付け、空間設計までもが“毎月・毎年同じものが出ない”よう緻密に設計されています。これは単なる形式的な変更ではなく、「変わり続けることで価値を更新し、お客様への感動を絶えず創出する」ための信念に基づくものです。(参考:「銀座 小十」が変わった理由。)
日本料理の世界は、四季や風土や行事を映す芸術でもあります。その中で「毎月異なる献立と器を準備する」というのは、効率性の対極にあるように見えて、実は職人やスタッフの緊張感と創意を維持する極めて実践的な仕組みでもあります。この姿勢は、食品製造業が直面する「ルーティンによる惰性」を乗り越える鍵として、大いに参考になります。
第2章:マンネリの正体──“やっているのに、響かない”現象
「またこの資料か…」と誰かがつぶやいた瞬間、その空気は職場全体に染みわたります。マンネリとは、表面的には“継続”に見えて、実質は“停滞”である状態を指します。
多くの現場では、同じフォーマットの報告書、形式的な朝礼、内容がルーチン化した改善提案などが“形”としては存在しています。しかし、参加者の表情はどこか義務的であり、言葉に魂が宿っていない——そんな光景を目にしたことがある方も少なくないのではないでしょうか。
この「やっているのに響かない」状態の背景には、心理学でいう「馴化(じゅんか)」という脳の特性があります。人は同じ情報、同じ形式、同じ刺激を繰り返し受けると、そこに注意を向ける必要がないと判断し、反応を弱めていきます。つまり、内容がどれだけ重要であっても、「見慣れたパターン」の中にあるだけで無意識にスルーされてしまうのです。
製造業においては特に、安全や品質が求められるがゆえに、手順や報告の標準化は避けられません。しかし、その構造の中にあっても、「形式ではなく意味が伝わる工夫」を差し込むことは可能です。
たとえば、ある企業では改善報告の文化を変えました。従来は書式に沿って記入するだけだった改善内容を、週1回の「3分プレゼン」に切り替え、最後には全員が拍手で評価する。報告者は自分の言葉で語るため、内容の本質を考え直すきっかけになり、聴き手も他部署の視点を知る機会となる。「伝える」「受け取る」双方に“感情”が生まれることで、形式が“意味”へと昇華されていくのです。
このように、マンネリとは“やり方の問題”ではなく“伝え方と受け取り方の再設計”で克服できる現象です。
第3章:脳科学に学ぶ──“飽き”とドーパミンの関係性
飽きるのは意志の弱さではなく、脳の機能です。人間の脳内には「報酬系」と呼ばれる神経ネットワークが存在しており、ここで中心的な役割を担うのがドーパミンという神経伝達物質です。
ドーパミンは「新しさ」「意外性」「達成感」などに強く反応します。新しいアイデアを得たとき、誰かに褒められたとき、困難を乗り越えたときにドーパミンが分泌され、脳は「それをもう一度やりたい」と感じます。一方で、同じ作業、同じ環境、同じ評価の繰り返しではドーパミンが減少し、意欲の低下が引き起こされていきます。
この理論は、職場における「刺激の枯渇」→「意欲の低下」→「マンネリ化」という悪循環を説明する上で非常に有効です。
製造業においても、脳科学の視点を取り入れた「意欲の再設計」が可能です。たとえば:
- 成果が評価される仕組みを、予測可能ではない“サプライズ的”要素を含めて設計する
- 小さな成功体験を積ませ、報酬よりも「できた」という達成感で行動を強化する
- 自分のアイデアが反映される、提案が形になるという「自己効力感」を演出する
ある自動車工場では、QCサークルの改善活動において、メンバーが交代で役割を担う「輪番制」を導入しています。提案者・発表者・記録者といった役割を定期的に入れ替えることで、日常業務の中に“意外性”と“自分ごと化”を織り込み、飽きの発生を抑えています。
また、ある飲料製造工場では、月に一度“工程交差体験”として他部署の仕事を体験する制度を導入しました。これにより従業員の視野が広がり、「同じ仕事でも意味のとらえ方が変わった」と語る声が多数上がっています。変化は意欲だけでなく、安全性や品質にもプラスに働くのです。
第4章:感情労働の視点──飽きさせない関係構築の技術
接客や販売といった“感情労働”の領域では、「相手の反応を読み取り、期待以上の体験を提供する」ことが成果に直結します。そのためには、表面的なサービス提供ではなく、「記憶・演出・感情の起伏」を駆使することが求められます。
たとえば、あるホテルチェーンでは、リピーターの来館日や好みをデータベースで管理し、次回来訪時には「前回おすすめした地酒、お口に合いましたか?」と自然な一言を添える。この一言が「自分を覚えてくれていた」という驚きと喜びを生み、再来訪につながっていきます。
この原理は、製造現場にも応用可能です。
たとえば、現場リーダーがメンバーの小さな改善や工夫に気づき、それを1対1のフィードバックや朝礼での紹介として“記憶される言葉”にすることで、「誰かが見てくれている」「自分の工夫が価値になる」という感覚が育まれます。
また、匿名で「今月のありがとうメッセージ」を書き合い、休憩室に掲示する取り組みでは、言葉のシャワーが職場の空気を変えました。人は感謝や称賛を“言葉として受け取ったとき”に、自己価値を再確認します。心の報酬は、金銭的インセンティブを超える“動機の源泉”になるのです。
第5章:組織心理の応用──物語と役割による共感の仕掛け
人は命令だけでは動きません。「私はこの組織の物語の一部だ」と感じられることで、初めて内発的に行動するようになります。これは、心理学における“自己物語理論”や“ナラティブ・アイデンティティ”の考え方にも通じます。人は自分の経験を“物語”として再構成し、それによって「自分の意味」や「居場所」を見出していきます。
この観点から見ると、職場の活動や制度が“無機質な指示”や“数字だけの目標”で構成されている場合、人は感情的に共鳴できず、やがて無関心になります。一方で、その活動に「なぜそれをやるのか」「誰のためになるのか」「自分はどんな役割を担っているのか」が語られると、物語の中に自分を位置づけることができ、行動が意味を帯びてくるのです。
【実在事例】
京セラの「アメーバ経営」では、小単位のチーム(アメーバ)が収支責任を持ち、チームリーダーは“小さな経営者”としての自覚と裁量を持って活動します。この仕組みによって、組織全体に「自分が組織を動かしている」という当事者意識が根づきました。
(参考:企業経営情報レポート「小集団チーム別採算管理の手法」)
また、ある食品工場では、「毎月の改善テーマ」を職場内でストーリー化し、発表者が“なぜこれを改善したか”“自分にとって何が変わったか”を語る文化が育っています。報告というより“語り”のスタイルにすることで、聞き手にも共感が伝播し、他部署との連携や模倣が自然に生まれました。
さらに、役割そのものに“意味づけ”を与える工夫も有効です。単なる「現場リーダー」ではなく「現場ナビゲーター」や「品質ストーリーテラー」といった呼称に変えるだけで、その役職が持つ期待やイメージが変化し、内面的な振る舞いまでもが変わるのです。
第6章:実践の蓄積──成功を生む仕組みと継続の型
マンネリ化は、単に「変化が足りない」から起こるわけではありません。むしろ問題なのは、「変化が偶発的で、継続的な仕組みにまで高められていないこと」です。
優れた現場では、変化を“制度”に落とし込むことで、「自然に更新される文化」を形成しています。
マニュアルシステムを導入したある食品メーカーでは、システム導入のタイミングで「毎月必ず何かを変える」というルールを定め、朝礼の進行方法、壁の掲示物、作業着の色、作業工程の説明スタイルなど、ささいなものも含めて“変化”を固定しました。それによって、変えることが目的化せず、「変わることで何が生まれるか」を職場全体が考えるようになったのです。
この企業では、年間の改善提案件数が2倍に増加。クレーム発生率が27%減少し、「変化を歓迎する風土」が育っていきました。重要なのは、「変えること」ではなく「変わり続けることをチームで支える構造」にあります。
さらに、「飽き」に対抗する工夫として効果的だったのが、以下のような仕掛けです:
- “推しメン”制度:月ごとに同僚の貢献を称え合う匿名推薦ボードを設置。感謝や賛辞を通じて仲間の努力が“見える化”され、承認と絆が生まれた。
- “語りの時間”の導入:月1回の会議を「テーマ発表型」から「ストーリー共有型」に切り替え、失敗談や工夫を人間らしく語る時間に変更。失敗に寛容で挑戦を歓迎する文化が醸成された。
- “変化カレンダー”の作成:1年に12回、必ず変える項目(掲示板、手順書レイアウト、報告方式など)を事前に決めておくことで、準備も含めて計画的な改善が実現。
このように、「飽き」を恐れるのではなく、「変化を織り込んだ設計」で日常そのものを再構成することで、継続的な成長サイクルが実現されるのです。
まとめ
飽きとは、怠慢ではなく自然な現象です。惰性とは、構造の産物であり、決して個人の責任にしてはいけません。
日本料理の名店「銀座 小十」が、月ごとに献立と器を刷新し、季節を繊細に織り込んでいくように。感情労働のプロが、一人ひとりの顧客に異なる演出で心を揺さぶるように。自律的な組織は、従業員の物語と成長を可視化し、全員で変化を育てていくのです。
そして、食品製造業の現場でも、「変わる文化」「語る文化」「称える文化」、そしてもうひとつ、「遊び心のある文化」を取り入れることで、ルーティンと惰性の間に“美意識ある揺らぎ”を生み出すことは十分に可能です。
飽きさせない組織には、意味があります。飽きさせない仕事には、物語があります。飽きさせない現場には、人の顔と声、そしてほんの少しのユーモアと柔らかさがあります。
マンネリとは、「もう変えなくていい」という思考の静止です。
だからこそ──変化を恐れず、時にくすっと笑える工夫を忍ばせながら、「変わり続けようとする姿勢」を組織に宿してみるのはいかがでしょうか。
それはきっと、組織をしなやかに、そして力強く生かし続ける源となっていくはずです。

利益改善コンサルタント
資格・スキル活用コンサルタント
技術士合格講師
小松 加奈 氏
日系大手製造業に勤務しながら(2007年新卒入社、技術系総合職)、複業として個人事業も展開している。
工場現場担当者の経験もある、現役会社員の技術士。最前線で『リアルタイム』の『現場』『現物』『現実』『最新技術』と日々向き合っている。
勤務先では、開発部・工場(開発課・製造課・生産管理課)・商品部・生産本部生産管理部にて、工場現場から、本部での管理業務、生産原価管理システム構築、新設工場の生産管理業務構築まで務める。原価改善プロジェクト多数実施。改善・原価教育多数実施。
個人事業では「製造業特化型コンサルティング」「完全カスタマイズ型コンサルティング(全業種対象)」「資格・スキル活用コンサルティング」「技術士合格講座(一般部門全20部門対象)」を展開。
科学技術分野の文部科学大臣表彰(文部科学省主宰)の技術審査員も務め、400件以上の製造業改善事例を審査。
利益改善に関するコンサルティングや、合格に導く技術士受験指導にも定評がある。
【 資格 】
技術士(経営工学部門)、第一種衛生管理者、ハム・ソーセージ・ベーコン製造技能士、フォークリフト運転技能、フードコーディネーター 他
利益改善コンサルタント 技術士 小松加奈website
24時間を楽にする技術【技術士 経営工学部門 小松加奈】
技術士が経営工学技術をもとに、『24時間公私ともに楽にする技術』を『誰でも今すぐ使える』形でわかりやすく伝授❗❗
【2週間ごとに金曜日19時投稿】
【本コラムに関する免責事項】
当サイトへの情報・資料の掲載には注意を払っておりますが、
最新性、有用性等その他一切の事項についていかなる保証をするものではありません。
また、当サイトに掲載している情報には、第三者が提供している情報が含まれていますが、
これらは皆さまの便宜のために提供しているものであり、
当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被ったいかなる損害についても、
当社および当社に情報を提供している第三者は一切の責任を負うものではありません。
また第三者が提供している情報が含まれている性質上、
掲載内容に関するお問い合わせに対応できない場合もございますので予めご了承ください。