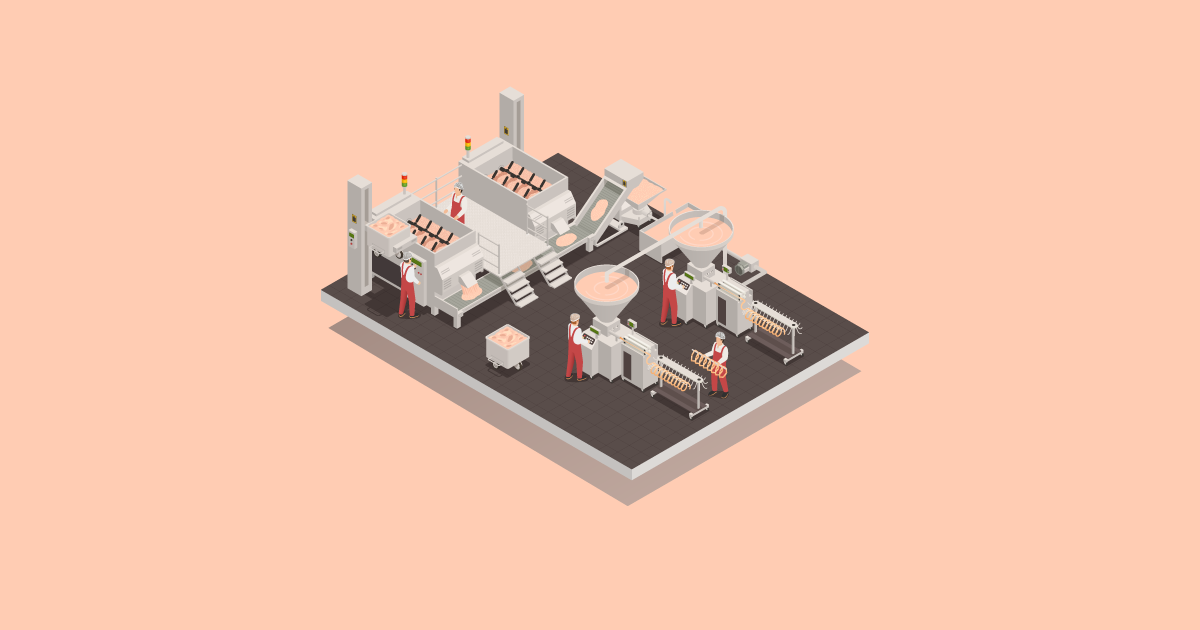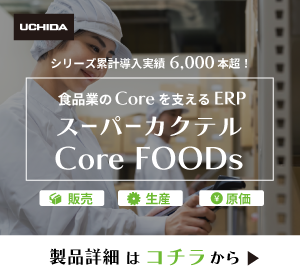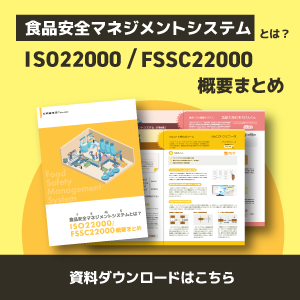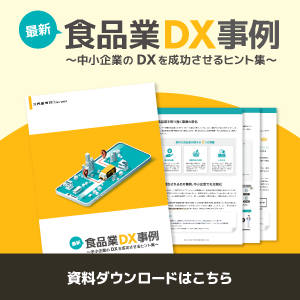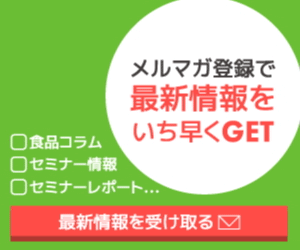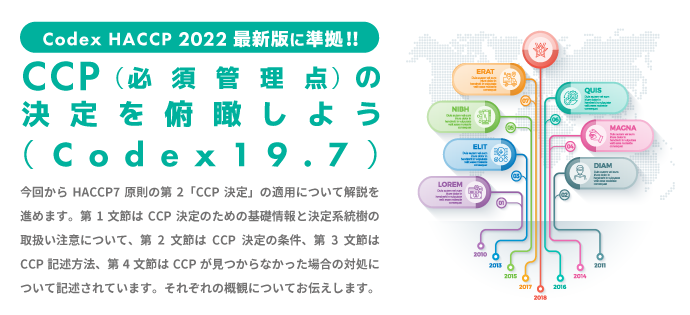
はじめに
今回から解説はHACCP12手順の7手順目、HACCP7原則の第2原則「適用」の解説に入らせていただきます。ここでは第58回から前回まで6回に分けて解説してきたハザード分析によって、特定された「重大なハザードに対するコントロール手段」に対し、ここからは「CCPとなるステップ」がどこかを考えていきます。
HACCP7原則の「原則2 CCPの決定」についてはすでに、第37回(2023.02.20公開)で「原則」の解説をしています。ここでは専門用語「必須管理点(CCP;Critical Control Point)」「HACCPシステム」「HACCP計画」「コントロールする(動詞)」「ステップ」の定義を詳しくご説明いたしました。以降の解説を読み解くのに欠かせない情報なので、まずは振り返り学習をいたしましょう。
決定系統樹“例”はすべての状況には適用できない
図に示した通り「19.7 必須管理点(CCPs)の決定」(手順 7 /原則 2)は4文節で構成されています。これを和訳文の文字数ベースでカウントすると、第1文節が598文字、第2文節が341文字、第3文節が81文字、第4文節が60文字と、文節ごとにかなり文字数(要は記述のボリューム)に差が大きいことがわかります。最も文字数の多い第1文節はCCP決定のための基礎情報と決定系統樹の取扱い注意について、次に文字数の多い第2文節はCCP決定の条件について、第3文節は決定したCCPの記述方法について、第4文節はCCPが見つからなかった場合の対処についてそれぞれ記述されています。以下、ざっと概観を確認してみましょう。
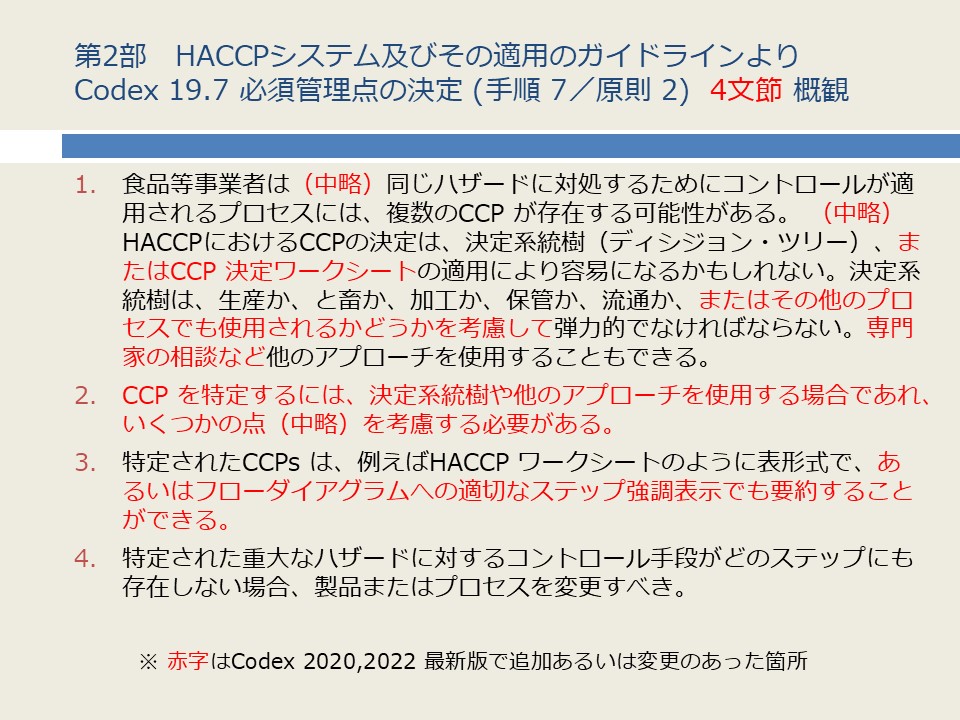
まず第1文節ですが、文字数が非常に多いため今回は「(中略)」とさせていただいていて、次回から細かく解説していきます。要するに前回で解説した「個々のハザードへのコントロール手段適用」から系統的にリンクするものであり、図にあるように「同じハザードに対処するためにコントロールが適用されるプロセスには、複数のCCP が存在する可能性がある」といった基礎情報が記述されています。次いで、CCP決定系統樹(ディシジョン・ツリー)についての記述が続きます。このCCP決定系統樹の適用についてはまた改めて解説(新たに追加されたCCP決定ワークシートも同様に…)いたしますが、「生産か、と畜か、加工か、保管か、流通か、またはその他のプロセスでも使用されるかどうかを考慮して弾力的でなければならない」とある通りで、旧2003年版には「すべての状況には適用できないだろう」とまで記述されていました。CCPを決定するときのガイダンスではあるもののあくまでも「例」でしかなく、うまく当てはまらないのに無理やり適用させようとすることはなるべく避けたいものですね。
クリティカル(必須)なステップは特定できるか
第2文節もそれなりの文字数なので以降に詳述するとして、ここは決定系統樹を使用するかしないかに関わらず、考慮するべきポイントが解説されている文節です。決定系統樹で共通に出されている“問い”としては「分析対象のプロセスステップでコントロール手段を使用できるかどうか」でしょうか。すっきりした新しい決定系統樹を作ろうと各国委員が知恵を出し合い、2020年更新時には議論が定まらず、さらに2年の議論を経て2022年版で確定できたものの上述した通り、すべてのオペレーションには適用できないとなり“一例でしかない”との表現に落ち着きました。以降に改めて詳述しますがやはり、「同じハザードに対処するためにコントロールが適用されるプロセスには、複数のCCP が存在する可能性がある」といった現場では決定系統樹は使い勝手が良くないようです。米国ではこの“合わせ技”でコントロールを保証する考え方を「ハードルアプローチ」と呼称して整理しようとしています。
CCPをどう文書化する? CCPがない場合は?
第3文節81文字の日本語訳の“本文ママ”は「特定されたCCPs は、例えば附属文書Ⅳ、表2 に示されているHACCP ワークシートのように表形式で、あるいはフローダイアグラムへの適切なステップ強調表示でも要約することができる」です。そして第4文節60文字の日本語訳の“本文ママ”は「特定された重大なハザードに対するコントロール手段がどのステップにも存在しない場合、製品またはプロセスを変更すべきである」となります。
第3文節81文字と、第4文節60文字は、図でお示しした通りの情報で必要十分条件を満たしています。ですが、第3文節では「HACCP ワークシート」と「フローダイアグラムへの強調表示」を解説しなければいけませんし、第4文節では、その「コントロール手段が存在しない場合」についてより具体的にイメージできるよう解説が必要なのではないかと考えています。
限られた文字数制限で今回お伝えしておくべき範囲での情報としては、「HACCP ワークシート」とはCCPとして定めたコントロールステップにおける、HACCP原則3~7を適用する計画書そのものです。一方で「フローダイアグラムへの強調表示」はこれを小規模営業者等でも適用しやすいような弾力的に考えたアプローチによる計画書だとお考え下さい。また、「コントロール手段が存在しない場合」の代表例は日本人も大好きな“生食”(なましょく)を例に挙げるとよく理解できるはずです。次回以降、個別事例やテクニカルな記述も増えると思いますがぜひ継続して購読ください。

著者が講師を務めるセミナーについてご案内します。詳細は以下のバナーよりご確認ください!(内田洋行のサイトに移動します)

月刊HACCP(株式会社鶏卵肉情報センター)
代表取締役社長
杉浦 嘉彦 氏
株式会社 鶏卵肉情報センター 代表取締役社長(2005年より)
一般社団法人 日本HACCPトレーニングセンター 専務理事(2007~2024年)
国際HACCP同盟認定 トレーナー・オブ・トレーナー
月刊HACCP発行人、特定非営利活動法人 日本食品安全検証機構 常務理事(農場HACCP認証基準 原案策定 作業部会員)、農林水産省フード・コミュニケーション・プロジェクト(FCP)ファシリテータ、東京都および栃木県 食品衛生自主衛生管理認証制度 専門委員会 委員、フードサニテーションパートナー会(FSP会) 理事、日本惣菜協会HACCP認証制度(JmHACCP) 審査委員、日本フードサービス協会 外食産業 JFS-G規格及び手引書 策定検討委員、その他多数
作れる!!法制化で求められる衛生管理計画への道筋
監修 一般社団法人日本HACCPトレーニングセンター
編集 株式会社鶏卵肉情報センター 月刊HACCP編集部
一般社団法人日本HACCPトレーニングセンター(JHTC)による事業者支援セミナーをテキスト化した一冊です。
【本コラムに関する免責事項】
当サイトへの情報・資料の掲載には注意を払っておりますが、
最新性、有用性等その他一切の事項についていかなる保証をするものではありません。
また、当サイトに掲載している情報には、第三者が提供している情報が含まれていますが、
これらは皆さまの便宜のために提供しているものであり、
当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被ったいかなる損害についても、
当社および当社に情報を提供している第三者は一切の責任を負うものではありません。
また第三者が提供している情報が含まれている性質上、
掲載内容に関するお問い合わせに対応できない場合もございますので予めご了承ください。