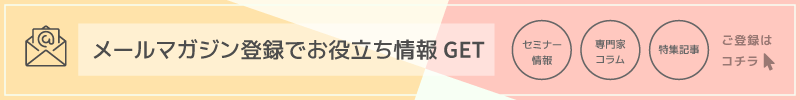INDEX
1.食品リコールとは?
2.自主回収(リコール)報告制度が創設された背景と目的
3.食品等リコール報告制度の対象範囲
4.食品リコール情報の届出の方法
5.食品等リコール報告制度のクラス分類
6.食品衛生申請等システムについて
7.食品リコール情報の届出の注意事項
8.罰則規定について
9.食品リコール制度のまとめ
10.食品リコールにつながる商品事故を未然に防止するために
食品リコールとは?
食品リコールとは、製造または販売された食品に食品衛生法や食品表示法に違反するもの、あるいはその恐れがあるものが発見された場合に、事業者が自らの判断でその食品を回収することです。
この制度は、消費者の健康被害を未然に防ぐことを目的としており、2021年6月1日からは、一部の例外を除き、食品リコール情報の行政への届出が義務化されています。届出られた情報は厚生労働省のシステムで一元管理され、公表されることで、消費者は迅速にリコール情報を確認できるようになりました。
自主回収(リコール)報告制度が創設された背景と目的
2021年6月1日から自主回収(リコール)報告制度が創設された背景には、食品の安全に関する問題発生時に、行政が迅速かつ的確に状況を把握し、消費者へ正確な情報を提供することの重要性が高まったことがあります。以前は、食品関連事業者が自主回収を行っても、その情報を行政機関に届け出る仕組みがありませんでした。これにより、食品による健康被害が発生したり拡大したりするリスクがありました。
このような状況を踏まえ、食品衛生法と食品表示法が改正され、事業者が自主回収を行う場合に、その情報を行政へ届け出ることが義務化されたのです。
この制度の主な目的は、消費者への情報提供を一元化し、リコール対象の食品を喫食してしまうことを防ぐことにあります。 また、行政がリコールに関するデータを分析し、改善指導を行うことで、食品衛生法や食品表示法への違反を未然に防止することも期待されています。
この制度により、事業者と行政が連携し、食品の安全性をより一層確保することを目指しています。
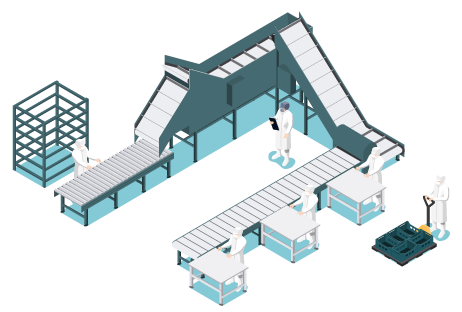
食品等リコール報告制度の対象範囲
報告対象
食品等リコール報告制度の対象となるのは、主に以下の3つのケースです。
(1)食品衛生法に違反する食品
腸管出血性大腸菌により汚染された生食用食品、アフラトキシン等発がん性物質に汚染された食品等。
(2)食品衛生法違反のおそれがある食品
食品衛生法違反となる原因と同じ原料を使用している、製品方法や製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として営業者が違反食品等と同時に回収する食品等。
例えば、製造工程上の不備や、異味・異臭、異物混入の苦情があり、健康被害のおそれが否定できない場合などが該当します。
(3)食品表示法に違反する
アレルゲンや消費期限等の安全性に関する表示の欠落や誤り。
報告対象から適用が除外される場合
- 当該食品等が不特定多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合
具体的には、地域の催事で販売され、会場での告知で回収が可能なケースや、外部者が利用しない企業内売店での販売などが該当します。 - 当該食品等を消費者が飲食しないことが明らかな場合
食品等が営業者間の取引に留まり倉庫に保管されている場合や、消費期限・賞味期限を大幅に超過している場合などが考えられます。
外部者が利用しない企業内の売店なら館内放送、通信販売なら顧客に対して個別に連絡するなど、購入者へ「すぐに」連絡をとれることが大切です。厚生労働省は適用が除外されるケースを細かく挙げています。
食品リコール情報の届出の方法
食品のリコール情報の届出は、厚生労働省が運用する食品衛生申請等システムの活用が推奨されています。食品関連事業者等は、食品の自主回収に着手した後、遅滞なく届け出る必要があります。届出先は食品関連事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事です。
ただし、特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品の表示違反による自主回収の届出など、消費者庁長官への直接届出が必要な場合もありますので注意が必要です。
食品表示法違反の自主回収の際には、フロー図から食品リコール情報の届出義務があるか確認することができます。食品ロス削減の観点から、自主回収に着手する前に表示の修正が可能か検討し、可能であればシールを貼るなどして対応することが望ましいとされています。
食品等リコール報告制度のクラス分類
届出された自主回収情報は健康被害発生の可能性を考慮した、クラス分類が導入されました。CLASS分類が明確に区分、分類できないケースもあり、CLASSが途中で変更されることがあります。
|
食品リコールによるリスクに応じたクラス分類 リスク大 ⇔ リスク小 |
|||
|---|---|---|---|
| 喫食により重篤な健康被害、または死亡の原因となりえる可能性が高い場合 | 喫食により重篤な健康被害、または死亡の原因となりえる可能性が低い場合 | 喫食により重篤な健康被害がほとんどない場合 | |
| 食品 衛生法 |
腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜など | 一般細菌数などの成分規格不適合の食品など (一般的な自主回収) |
添加物の使用基準違反など |
| 食品 表示法 |
アレルゲンの欠落など | 安全性に関する表示違反でCLASS1以外のもの | |
食品衛生申請等システムについて
政府のデジタル化を進める流れに沿って届出のオンライン化も始まりました。
食品衛生申請等システムは、厚生労働省が運用しており、食品等事業者による営業許可の申請や届出、食品リコール情報の報告をオンラインで行うために導入されました。報告された情報は厚生労働省のホームページで公表され、事業者は広範囲に情報を伝えることができ、消費者も自主回収に関する情報を迅速に入手できるようになります。
食品リコールという緊急時にどう対応するのか、事業者各社、さまざまなルールが定められているかと思います。自主回収は迅速に実施しなければならないため、事前に食品等事業者情報登録を行い、IDとパスワードの取得・情報共有が望ましいでしょう。
自主回収を届出する際には写真をアップロードする必要がありますが、あくまで自主回収のため、届け出の文面や写真のわかりやすさは各事業者に委ねられています。
食品リコール情報の届出の注意事項
公表
全て食品衛生申請等システムにより公表されます。
任意の届出
食品表示基準違反に係る食品の自主回収について、任意で届出を行うことができます。 任意での届出や消費者への情報提供は、消費者安全の観点から望ましいとされています。
食品ロス削減の推進
消費者庁は食品ロス削減の所管官庁でもあるので、食品リコール報告制度においても食品ロス削減に配慮するよう求めています。
食品ロスの削減推進を目指し、事業者には自主回収以外にも表示の是正など、食品を有効活用し、過剰な食品ロスを防ぐための適切な対応が期待されています。また自主回収した食品であっても、食品衛生上の問題がなく、表示の是正が可能な場合については、食品表示を修正して販売するなど、食品ロス削減に向けた取り組みを推進することが望ましいとされています。
罰則規定について
食品関連事業者等がリコール情報の届出を行わなかった場合や、虚偽の届出を行った場合には、罰則が科される可能性があります。食品衛生法および食品表示法には、それぞれ罰則に関する規定が設けられています。
具体的には、食品衛生法においては、自主回収の届出を行わない、または虚偽の届出をした者に対して、50万円以下の罰金が科されることがあります。(食品衛生法第85条第3号)
また、食品表示法においても同様に、自主回収の届出をせず、または虚偽の届出をした場合には、50万円以下の罰金に処されることが定められています。(食品表示法第21条第3号)
これらの罰則は食品リコール情報の適切な報告を促進し、消費者の健康被害を防止することを目的としており、事業者には制度の遵守と正確な情報提供が求められています。
食品リコール制度のまとめ
届出はオンライン上のシステムを利用するため、届出のフローを理解(アカウントの作成、緊急時の担当者決め、消費者庁簡易マニュアルを事前確認)すると、緊急時に迅速に対応できるでしょう。
届出の対象とともに、食品衛生法違反、違反のおそれか、食品表示法違反か、違反のおそれか、分類や法律についても理解する必要もあるでしょう。またCLASS分類は都道府県が行いますが、その判断のための情報を正確に伝えることが食品事業者へ求められています。
食品リコールにつながる商品事故を未然に防止するために
食品衛生法関連の原因は、異物混入(プラスチック片の混入等)、カビの発生、規格基準違反(一般生菌数、大腸菌群等)が多く、食品表示法関連の原因は、ラベルの印字ミス、貼り間違えが多く見受けられます。
いずれも、日ごろの衛生管理、工程管理の徹底等で防ぐことができます。さまざまなリコール事例を見ることで、原因・対策を考えることが出来るかもしれません。消費者へ安全を提供するためにも、食品リコール報告制度を使って品質管理を強化してみてはいかがでしょうか。
【参考】
・厚生労働省「自主回収報告制度(リコール)に関する情報」
・消費者庁食品表示企画課「食品表示法に基づく自主回収報告制度について」
・厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課「食品など自主回収(リコール)報告制度の創設に関するQ&A令和3年5月31日」
・消費者庁「食品表示法の一部を改正する法律の概要2021年6月1日施行」
・消費者庁食品表示企画課「食品表示法第10条の2に 基づく食品リコール情報届出制度」
・消費者庁「食品表示法第10条の2第1項の規定に基づく食品の自主回収の届出について(令和3年2月26日付食品消費者庁第80号次長通知)」
・消費者庁「食品表示法第10条の2第1項の規定に基づく食品の自主回収の届出に係る電子申請システムへの主食容量及び記載要領に関する留意事項について 令和3年5月24日」
・東京都福祉保健局「食品等の自主回収(リコール)報告制度について」
・神奈川県「食品等のリコール情報届出制度について」