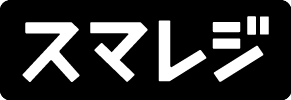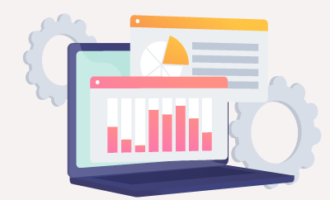INDEX
1.フードテックとは?
2.フードテックが求められる理由――SDGsとのかかわり
3.国策としてのフードテック ~政府の取組み~
4.代表的なフードテック活用事例
5.食品業でできるフードロス削減
6.よくある質問

フードテックとは?
現在、食領域で急速に研究が進む一連の最新科学技術は、“食(Food)”と“技術(Technology)”、二つの言葉を組み合わせてフードテックと総称されます。
経済産業省は同概念を「サイエンスとエンジニアリングによる食のアップグレード」と定義づけ、農林水産省は「生産から加工、流通、消費等へとつながる食分野の新しい技術及びその技術を活用したビジネスモデル」と説明しました。
新食材の開発からAIやロボットの活用までその種類は多岐にわたり、投資額は世界で年間2兆円超。今後、その市場規模は700兆円にのぼるとも試算されています。コモディティ化が進む食品産業にとって、新たな付加価値をもたらす大きなビジネスチャンスといえるでしょう。
日本におけるフードテックへの投資額は?
食産業が成熟産業とみなされる日本においては、残念ながらフードテック分野への投資額は海外先進国ほど大きくはありません。2022年のデータで、米国におけるフードテック分野への投資額3兆1,000億円、中国1兆1,000億円に対し、日本ではわずか700億円となっています。ただ、スタートアップへのサポートの不十分さについては課題と捉えられており、特許庁はフードテック分野に挑戦する企業を知財面でサポートする姿勢を示しています。
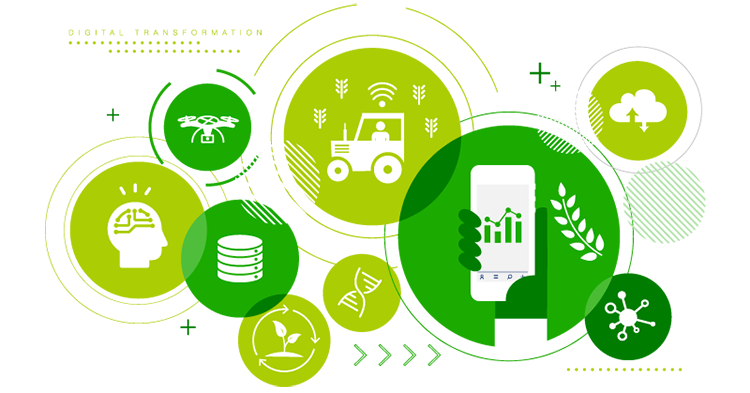
2021年、農林水産省は持続可能な食料システム構築をめざす取組みとして「みどりの食料システム戦略」を発表しました。
同戦略においてもフードテックはその柱に位置づけられ、様々な社会問題を解決する原動力としての役割を期待されています。
食分野から社会問題解決に取り組むことは、取りも直さず食品業が抱える課題を解決することにも繋がります。いまフードテックが求められる背景について、もう少し深掘りしてみましょう。
フードテックが求められる理由
――SDGsとのかかわり
前述したみどりの食料システム戦略の取組み範囲は、調達・生産・加工流通・消費と食に関する全領域に及び、それぞれ脱炭素化・環境負荷軽減、イノベーションなどによる持続的生産体制の構築、持続可能な加工・流通システムの確立、持続可能な消費拡大や食育を推進しています。本戦略は、2015年に採択された持続可能な開発目標(SDGs)を受けて策定されました。
SDGsは持続可能な未来を築くための17の目標を掲げたものですが、フードテックの発展、また、食品業に携わる事業者の協力なくして達成することはできないでしょう。
持続可能な食料供給は喫緊の課題
スーパーやコンビニに行けば安全性の高い食品が手軽に買える現代日本では意識しづらいことですが、国連の発表では2021年時点の飢餓人口は8億2,800万人とされています。世界的にみれば人口と食料需要は急速な増加傾向にあり、近い未来、問題の深刻化は避けられません。SDGsに掲げられる17の目標でも「飢餓をゼロに」が二つめに並び、重要視されていることが窺えます。
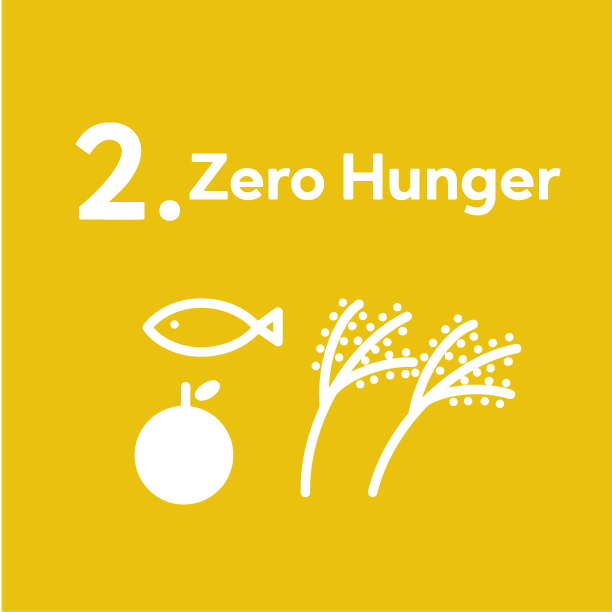
一方で、FAO(国際連合食糧農業機関)のレポートによれば、世界では食料生産量の3分の1に当たる13億トンが毎年廃棄されています(フードロス/食品ロス)。食を取り巻く環境は、きわめていびつな状況にあるといえるでしょう。
大量のフードロスの元凶と目される先進国においても、さまざまな混乱が起こっています。新型コロナウイルス禍や現在進行形のロシア・ウクライナ問題でサプライチェーンが大打撃を受け、食料品価格は暴騰中。生産人口減少も止めようがなく、食料の安定供給は、今後の大きな課題です。
環境負荷を食領域から考える
みどりの食料システム戦略やSDGsで、フードロスのほかに大きな課題とされているのが気候変動への対応です。
食の生産から加工、廃棄に至るまでのライフサイクルにおいては、CO2などの温室効果ガスや排水の排出、農薬や化学肥料の使用や農地転用に伴う森林開発といった環境負荷が生じる可能性があります。例えば、平均的な日本人の食事に伴うカーボンフットプリントは年間1,400kgCO2e/人と試算されており、肉類・穀類・乳製品の順でカーボンフットプリントが高いといわれています。
カーボンニュートラル実現のために、食品業界が担う役割はけっして小さくありません。
フードテックには、こうしたさまざまな社会課題を解決する原動力としての役割を期待されています。
国策としてのフードテック ~政府の取組み~
世界の食料需要量が2050年には2010年比で1.7倍(58億トン)になる見通しであること、また、海外でフードテックの社会実装がいち早く進展していることを受け、日本政府もフードテックには高い関心を払っています。
日本政府はフードテックについて「社会的課題の解決につながり、また、食に求める人々のニーズの多様化に対応する新たなビジネス」、あるいは「個人と社会全体のWell-beingを実現するうえで重要な技術」と高く評価しており、さまざまな取組みを実施しています。
1.フードテック官民協議会
食・農林水産業の発展や食料安全保障の強化に資するフードテックなどの新興技術について、協調領域の課題解決や新市場開拓を促進するため、2020年(令和2年)10月に産学官連携によるフードテック官民協議会が立ち上がりました。
フードテック官民協議会の目的に賛同する個人で構成され、食品企業やスタートアップ企業、研究機関、関係省庁などを中心に、2024年(令和6年)11月時点で約1,400人が参加しています。
2.フードテック推進ビジョン及びロードマップ
日本発のフードテックビジネスを育成することで日本と世界の食料・環境問題の解決に貢献するとともに、日本を活性化する新しい産業を創出し、経済の発展に貢献することを目的に、2023年(令和5年)2月21日フードテック推進ビジョン及びロードマップが策定されています。
本ビジョンにおいて目指す姿として掲げられたのは大きく3つです。すなわち(1)世界の食料需要の増大に対応した持続可能な食料供給、(2)食品産業の生産性の向上、(3)個人の多様なニーズを満たす豊かで健康な食生活。
これら3つを実現するために、スタートアップへの資金投入を含むプレーヤーの育成、国際整合性を踏まえたルール整備と消費者への啓蒙を含んだマーケット創出に向けた取組みが推進されています。2023年(令和5年)10月25日に更新されたロードマップでは、植物由来の代替タンパク質源、昆虫食・昆虫飼料、スマート育種のうちゲノム編集、細胞性食品、食品産業の自動化・省力化、情報技術による人の健康実現について、2025年度以降も引き続き取組まれることが示されています。
食品産業の自動化・省力化については、下記の記事も併せてご確認ください。
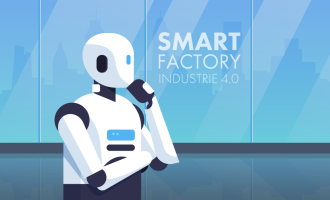
食品業のスマートファクトリー3大事例
2024年最新版
3.フードテックビジネス実証事業
新事業の創出や食品産業の共通課題に対し、実証などの取組みを支援する施策を一体的かつ総合的に推進することを目的に、予算事業として補助金などの各種支援策が実施されています。フードテックビジネス実証事業に係る公募要領については、農林水産省Webサイトからご確認ください。
代表的なフードテック活用事例
さまざまな社会問題の解決に向けて現在、世界各国で研究と実用化が進むフードテック。本項では、その代表的な事例をご紹介しましょう。
1.代替食の開発
将来的な食料不足、また、持続可能性の高い食品を求める消費者動向を受け、現在、急速に認知度を伸ばしているのが代替食品です(図)。
植物由来食肉様食品(PBM)
例えば植物由来食肉様食品(PBM;Plant Based Meat)は、小売や外食の場面でも、すでに珍しいものではなくなりました。大豆や穀類などを原料に食肉の食感と風味を再現したもので、口にしただけでは容易に区別できないほどです。
PBMは、単純に肉の代替というだけではありません。従来の家畜肉よりも環境への負荷が小さいとされ、また、現代社会において多様化する食のニーズに応える技術でもあります。実際に海外では、動物性タンパク質の摂取を避けるベジタリアンやヴィーガンから注目が集まっています。
一方、日本では主に健康食品の一環として注目されているようです。動物性タンパク質の代わりに大豆食品などの植物性タンパク質をより多く摂取すると死亡リスクが低下するという研究が数多く報告されており、植物性タンパク質は健康に良い影響をもたらすとの見方が優勢です。価格・値段が高いのが難点ですが、普及が進めばより身近な食材になるでしょう。
細胞培養肉
家畜から採取した細胞をもとに作る細胞培養肉も、拡大する食料需要をみたす有力な解決策のひとつです。2013年にオランダで開発された世界初となる細胞培養肉ハンバーガーは、1個当たり25万ユーロ(約3,000万円)と、コスト面で課題を抱えていました。ただ、現在ではわが国でも大手食品メーカーが続々と研究に参画、大幅なコスト減を実現しつつあります。
よく知られる国内の事例が、大阪大学などの共同研究グループが3Dプリンターを活用して開発した食用培養肉技術です。霜降りの和牛肉に近い培養肉を作れるというもので、各種メディアでも大きく取り上げられました。こちらは大阪万博でも展示され、社会実装への弾みがついた恰好です。
培養肉の法律上の扱いは?
2023年、イタリアでは培養肉などの細胞性食品の生産や販売を禁止する法案が賛成多数で可決されています。食の伝統を守れなくなるという理由からのことで、お国柄がよく表れた法律といえるでしょう。
2025年1月現在、日本において培養肉について規制する法令はありません。一方で、日本の食品衛生法には「これまで人間が食べてこなかった全く新しい食品(新開発食品)」を規制するためのルール整備が為されています。つまり、開発・販売は自由に行なえるが安全性を鑑みて禁止されるケースも考えられるということであり、こうした法規制の動きについても業界から注目が集まっています。
昆虫食
昨今、取り沙汰される昆虫食も代替食のひとつに分類できるでしょう。日本でも一時期、食用コオロギが耳目を集めましたが、フランスでも昆虫食は主要な研究領域のひとつに位置づけられています。
2021年5月3日、EUが新規食品として昆虫を初承認したニュースは記憶に新しいところです。承認されたのは乾燥イエロー・ミールワーム(チャイロコメノゴミムシダマシの幼虫)を原料とする食品で、2023年までにはさらにコオロギやトノサマバッタなど複数種類の昆虫食で安全性が認められ、EU市場での販売が許可されました。消費者の昆虫食への心理的な抵抗を考慮して、プロテインバーやスナックなどから展開する動きが目立ちます。
なお、初めて販売承認を得た昆虫食品製造EAPグループのアグロヌトリスの新工場建設計画は、フランスの投資プロジェクトのひとつに選ばれており、830万ユーロの支援を受けることになっています。
こうした背景には、昆虫が単に脂肪・タンパク質・ビタミン・繊維・ミネラルを多く含み栄養価が高いというだけでなく、生産プロセスで温室効果化ガスを排出しない環境負荷の低さにも期待が集まっているからです。
完全栄養食
近年、スーパーやコンビニで完全栄養食(完全食)を謳う商品を見かけることが多くなりました。実際に2019年以降、完全栄養食市場は急速に拡大しており、大手食品メーカーやスタートアップ企業の別なく、開発がさかんに進められています。
完全栄養食とは、一般に厚生労働省「日本人の食事摂取基準」に基づき1食あたりに必要とされる栄養素を1つの食品で満たすものと定義されます。ドリンクタイプ(粉末飲料など)、主食タイプ(パンやカレー、麺など)、補助食品タイプ(バー、クッキー、グミなど)などバラエティに富んだ商品があり、食事の状況や好みに応じて、手軽に栄養バランスを補えます。まさに、タイパ・コスパが重視される現代ならではの食品といえるでしょ<う。
味の向上もめざましいほか、災害時の備蓄食としても有用であり、最も身近なフードテック事例といえます。
海外でのフードテック動向は?
フードテック分野への投資額が最も大きいアメリカでは、特に事例が豊富です。大豆・エンドウ豆やココナッツ油由来の脂質を用いた植物性タンパク質食品の開発・販売がさかんであるほか、2023年6月には鶏由来の細胞性食品について製造販売が承認されました。その他、植物工場でのイチゴの量産化が実現しています。
米国・ヨーロッパ以外では、シンガポールもフードテック先進国に数えられており、国内外からの投資によって代替タンパク質食品の製造工場設置の動きが加速しています。植物性代替肉のほか、大麦原料の代替ミルク、カニやエビといった甲殻類の培養肉製造の動きもあり、注目を集めています。
2.環境配慮型エネルギーへの転換
現在、エネルギーの主軸を占める化石エネルギー(石油や石炭)から、より環境負荷が小さいとされる代替エネルギーへの転換が活発化しているのはご存知のことでしょう。そうした分野でも、フードテックがひと役買おうとしています。
農業機械の電化はもとより、家畜の排せつ物や農作物非食部位(野菜くずなど)といった動植物を原料とするバイオマスエネルギーの活用も、カーボンニュートラル実現に向けた代表的な施策のひとつ。効率的なシステム構築と低コスト化を実現できれば、有用な代替エネルギーになりうると目されています。
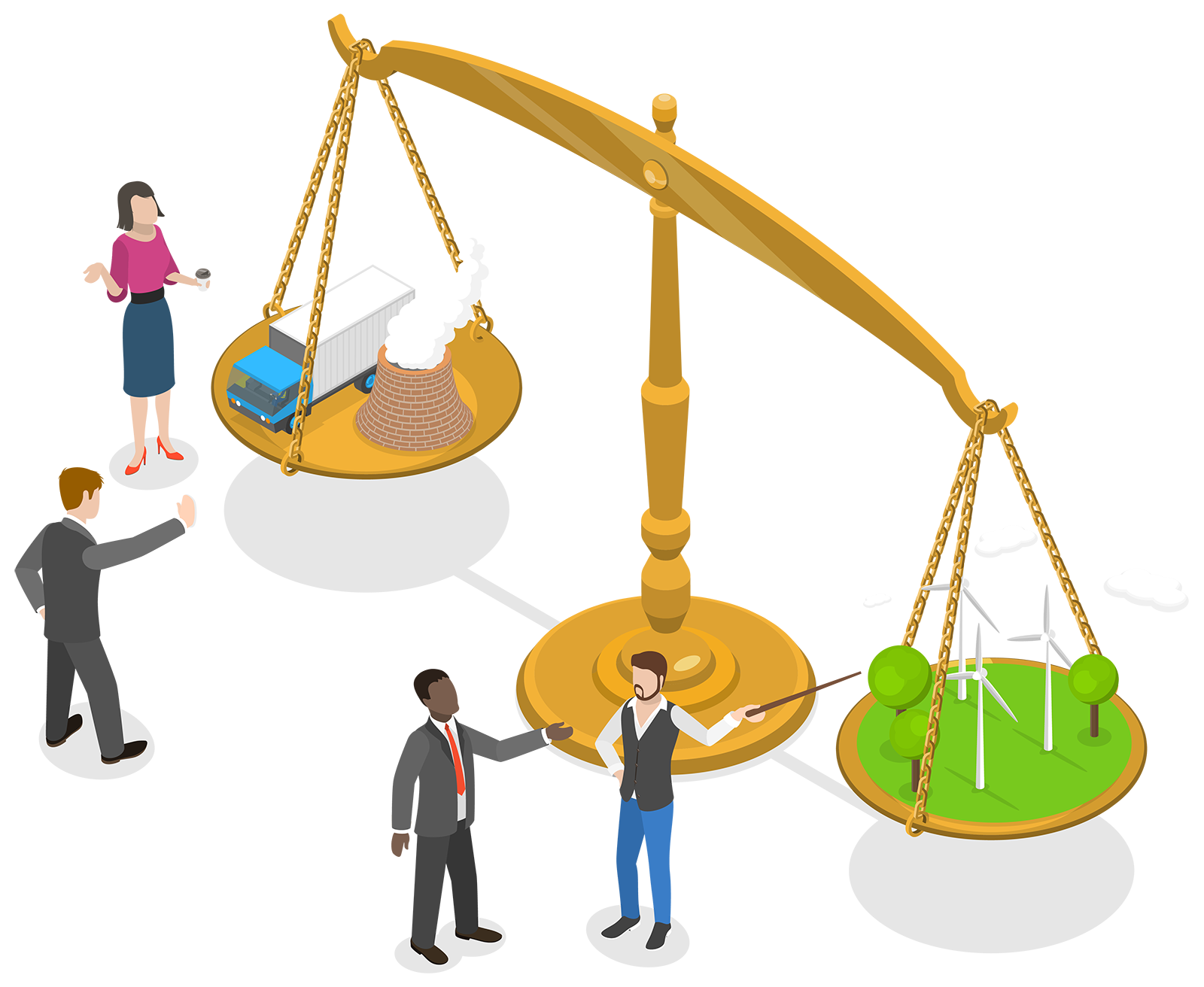
3.スマート技術の活用
ロボットやAI、IoTなどのスマート技術も、いまや食品業においてなくてはならない存在です。以下に活用例を列挙します。
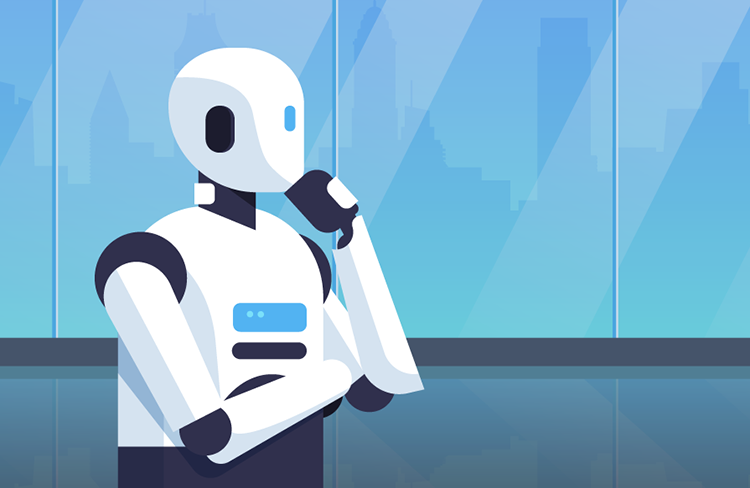
ロボット
第一次産業の舞台では農薬散布ドローンや無人農機が、第二次産業の分野でも調理ロボットによる製造工程の省人化が進んでいます。第三次産業でも配膳ロボットがすでに実用化され、親しまれていることはご存じのとおりです。
この分野でとりわけ大きなイノベーションとして知られているのが、Google社が開発した農業ロボット“Don Roverto”です。
Don Rovertoは、農作物の品種改良に必要なデータ収集を効率化するために開発されました。この農業ロボットは、テストフィールド内の農作物の画像を撮影し、機械学習を通して葉の数・面積・色、花の数やさやの寸法などの特性をもとに個体識別を行ない、それぞれの成長データを観測することで、気温の上昇や干ばつに耐性を持つ苗を見つけ出し、品種改良のスパンを高速化させることに寄与します。
フードテックとアグリテックの違いは?
アグリテックとは農業(Agriculture)とテクノロジー(Technology)を組み合わせた造語で、日本では「スマート農業」という呼び名が一般的です。ロボット・AI・ドローンなどを駆使した新しい農業の在り方を実現する最新技術全般を指し、フードテックと一部重複する、あるいは厳密に区別されていない技術も含まれます。すなわちフードテックとは、スマート農業やスマート水産業を包括した概念といえるでしょう。

5分でわかるスマート水産業!
水産改革のカギはDX
AI
先に紹介した農業ロボット“Don Roverto”の例だけでなく、AIもまた、食領域のさまざまな場面でなくてはならない新技術としてその地位を確立しています。
第一次産業では、天候・温度・土壌成分などの情報を基に最適な農作業の選定や病害虫の予察に役立てられており、第二次産業でも深層学習(ディープラーニング)を活用した高精度の画像認識で自動検品を実現しています(参考記事:食品工場スマート化3大事例 2022年最新版)。
国内一部地域では、AIを活用した自律走行ロボットによるフードデリバリーサービスが開始されました。自律のほか遠隔監視操作のもと安全基準に準拠して走行することが可能です。その他、AIを活用した完全無人営業のスマートコーヒースタンドなどの実用化事例も報告されています。

食品業のAI・自動化活用事例3選!
今後の動向を解説
IoT
生産や製造の現場だけではなく、流通の場面でもIoTをはじめとするスマート技術はすでに欠かすことができません。経済産業省は、電子タグ(RFID)や電子レシートの導入によるサプライチェーンのスマート化・最適化の実証実験を行なっています。これまで把握できなかったデータを解析し、その結果をサプライチェーンで共有することで在庫の可視化に繋がり、フードロス削減の一助となることが期待されています。
スマートボックスとは?
ヨーロッパで開発と導入が進む、RFIDを組み込んだオリコンのことです。ECの拡大などによりパレットロードを割る小ロット輸配送が増加するなか、わが国でもスマートボックスの導入・活用を早期に進める必要性が高まっています。
食品業でできるフードロス削減
ここまで持続可能な食料供給やフードロス削減といった社会問題を解決すべく推進されるフードテックについてお伝えしました。フードテックは総じて大きな投資を必要とし、黒字化も難しい分野です。自社だけで取組める事業者は、それほど多くないでしょう。
ただ、一方でフードロスは、すべての食品業事業者にとって深刻な課題です。フードテックの開発や導入まではできなくとも、在庫管理の適正化はあらゆる事業者が積極的に取組む必要があるでしょう。それは単にSDGsの問題というだけではありません。燃油や食料品価格の高騰が止まらないなかで適正利益を確保するための生命線といえるものます。
内田洋行ITソリューションズでは、製造から卸・小売まで、食に関する全領域で、在庫管理とフードロス削減を支援するシステムをご案内しています。
また、今回の記事で取り上げたフードテックについては、弊社発行の専門情報誌「食品ITマガジン」のVol.13でも取り上げています。マガジンのダウンロード/定期購読はいずれも無料ですので、ご関心のある方はぜひこちらもご活用ください。また、食品業のDX事情をお伝えする資料もご用意しています。併せてご活用いただけますと幸いです。
よくある質問
- Q.フードテックとはなんですか? どういう意味ですか?
- A.食と技術をそれぞれ意味する英語、FoodとTechnologyを組み合わせた造語(Food-Tech)です。
- Q.なぜフードテックに注目が集まっているのでしょうか。
- A.人口増加を背景にした食糧危機やSDGsの観点で課題となるフードロスなど、食品業界は現在、多くの困難な課題を抱えています。それらを解決することを目的に、さまざまな種類のフードテックに注目が集まっています。単に社会問題を解決するだけでなく、AIやIoTを用いることで生産性を大幅に向上させるなど、食品業事業者にとっても利点(メリット)の大きな取組みです。
- Q.フードテックにデメリットや問題点はありますか?
- A.フードテックの研究開発には、当然ながら設備投資や技術開発に関して莫大なコストがかかります。資金に余裕のある企業しか参画しづらいといえます。また、ゲノム編集による新たな食品も研究されていますが、それらを普及させるためには安全性を証明して消費者の理解を得る必要があるでしょう。官民挙げての取組みとはいえ、簡単にできることではありません。
- Q.記事内で紹介されたもののほかに、どんな種類のフードテックがありますか?
- A.農林水産省が令和5年(2023年)に発表しているロードマップによれば、3Dフードプリンターやドリンクプリンターなどの新技術も促進対象となっています。硬さや栄養素の調整することで、よりパーソナライズされた介護食を提供するなど、さまざまな活用が可能な新技術です。その他、AIを活用したレシピサービスなどもフードテックの代表的な具体例です。農林水産省のロードマップに一覧が掲載されていますので、詳細についてはそちらもご覧ください。
- Q.フードテックの安全性は?
- A.各国で新食品の製造販売についての承認が順次進んでいます。日本ではアレルギー低減卵や塩味を補強する減塩スプーンなど、安全性や健康に配慮した研究がさかんです。
- Q.フードテックはアレルギー症状対策にも役立ちますか?
- A.食物アレルギーの原因では、鶏卵が1位となっています。鶏卵の主要なアレルゲンであるオボムコイドは、加熱してもアレルゲン性を失いません。こうした課題をもとに、ゲノム編集技術でオボムコイドを含まないアレルギー低減卵の開発研究が進んでいます。また、アレルギー性物質を検知する小型デバイスの開発も進んでいます。
- Q.フードテック2.0とはなんですか?
- A.日経産業新聞は、安定的な拡大生産性のハードルを越えたスタートアップ企業の出現を指して、第2のフードテック、「フードテック2.0というべき」と表現しています。当該記事は、フードテックがごく一部の高価な嗜好品的な位置づけからブームを超えて必要不可欠な一般商品に成長していくことを期待する一文で締めくくられています。
- Q.植物由来食肉様食品(PBM)は健康によいのでしょうか?
- A.植物由来食肉様食品(PBM)は一般的に健康によいと見られますが、一方で動物性食品は必須アミノ酸をバランスよく含む良質なタンパク質であり、植物性食品はリジンなど不足している必須アミノ酸があることが指摘されています。また、植物性食品のみを接種する場合、ビタミンB12やカルシウム、鉄などといった栄養素も不足する可能性が高く、近年の研究においてはベジタリアンの方が出血性脳卒中や骨折のリスクが高いことが報告されています。バランスを考えた栄養摂取は必須といえるでしょう。
【参考】
・農林水産省「みどりの食料システム戦略」
・農林水産省「トピックス7 フードテックの現状」
・農林水産省「食品ロスの現状を知る」
・農林水産省「新事業創出(フードテック等)」
・農林水産省「フードテックをめぐる状況」
・農林水産省「フードテック推進ビジョン」
・農林水産省「フードテックの海外・国内のトレンド」
・農林水産省「ヘルスフードテックWT提案報告」
・農林⽔産技術会議事務局「研究開発に係る最近の情勢について」
・World Health Organization (WHO)「UN Report: Global hunger numbers rose to as many as 828 million in 2021」
・国際連合広報センター「飢餓をゼロに」
・独立行政法人 農畜産業振興機構「各国における食肉代替食品の消費動向」
・独立行政法人 農畜産業振興機構「米国における食肉代替食品市場の現状」
・経済産業省「令和3年度 流通・物流の効率化・付加価値創出に係る基盤構築事業 IoT技術を活用した食品ロス削減の事例創出」
・経済産業省「IoT等を活用したサプライチェーンのスマート化」
・METI Journal「経産省がなぜフードテックの旗を振るのか」
・環境省「サステナブルな食に関する環境省の取組について」
・日本貿易振興機構「EU、新規食品として昆虫を初承認」
・日本貿易振興機構「植物性代替肉や培養肉企業の集積加速 シンガポール、代替タンパク質の一大拠点へ(前編)」
・「FOOD TECH Lab(フードテックラボ)」
・国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「フードチェーンにおける食品ロスの現状と削減に向けた技術的課題」
・The Spoon「Meet Don Roverto, X’s Robotic Rover on the Hunt for The Next Magic Bean to Feed a Hungry Planet」
・日経産業新聞「動き出すフードテック「2.0」」
・キユーピー株式会社 研究開発本部「卵アレルギーに不自由のない世界の実現に向けて」
・財務省「代替肉市場について」